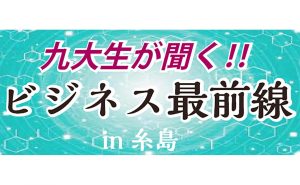江戸時代末期の女流歌人であり勤王活動にも関わった野村(のむら)望東尼(ぼうとうに)。彼女は、乙丑(いっちゅう)の獄で姫島へ遠島され、その後高杉晋作の命により救出され、幕末の激動期の中で生涯を閉じた。
歌集『向陵集(こうりょうしゅう)』をはじめ、『上京日記』、『夢かぞへ』、『比賣嶋(ひめしま)日記』などの著作があり、また、多くの手紙も残っていて『書簡集』としてまとめられている。
詠歌やその生涯に関する論考は数多くあるので、詳細を知りたい人は専門書にあたることをお薦めし、ここでは望東尼が姫島にて過ごした10カ月のうち、正月前後の様子を、直筆を基に紹介してみたい。

交替で食事の世話
慶應元(1865)年11月15日に「波あららかにうねりて、心地さへぞわづらわしく(=波が荒くて生きた心地がしなかった)」(夢かぞへ=以下、夢)と大変な思いをしながら姫島に到着し、「畳も無く板敷にて、いといかめしき(=見るからに恐ろしい)囚屋(ひとや)」(夢)での獄中生活が始まる。
先を思い、心細い心境は著述に見えるが、姫島の住民はそんな彼女に温かく接した。また、役人も大目に見ていた節があり、『書簡集』などを見る限り、比較的自由に手紙のやりとりと、物品の差し入れが行われている。
食事は藩指定の「喜平次方おふぢおや」、「むかへの家佐吉おとら方」、「となり家次三郎おみき方」(書簡集=以下、書)がひと月交替で世話をした。
詳細は割愛するが、差入れにいたっては身の回りの生活用品一式から薬、書や茶に関する道具までと、およそ幕藩体制の中の囚われ人とは思えないような品々を実家から取り寄せていることが書簡中の「入用之品々覺(=覚)」に見える
すぐに迎えた正月
さて、姫島に流されてすぐに年末と正月を迎えるのだが、『書簡集』には島民からの差し入れの詳細が記される。「年の暮貰ひ物」では「鏡餅」、「かずのこ」、「黒豆」、「砂糖」、「めばる入付」、「香の物」、「栗餅」など、誰から何をもらったかが克明に書かれている。年が明けた正月の書き出しは「年のはじめ」とあり、いきなり差し入れの「めばる」から始まり、「こしあん入りもち」、「小さざえ」、「黒ざたう(砂糖)」などが列記されている。
「元日二日三日はおみき方より雑煮」をいただいており、「一日もち十たべ申候(もうしそうろう)。雑煮の具 あはび、きりみ、するめ、やまいも、ごばう、さといも、こぶ、きやうな(京菜か)、しひたけ」と続く。なんとも豪華な雑煮であると同時に、その健啖(けんたん)(=好き嫌いなく食べること)ぶりが面白い。翌「二日七つ 俱 きりみ、あはび、しひたけ、にんじん、きゃうな」、さらに「三日七つ きりみ、きゃうな、しひたけ」とある。
4日は「お藤方より」となっており、「ざふに 九つ あはび、きりみ、こんぶ、するめ、山いも、ごばう、きやうな」である。日付の後の数字は、最初は時刻を表わしているかと思ったが、四日の書き方から、どうやら雑煮に入る餅、あるいは食べた餅の数のように思える。
雑煮の他にも、「おはづけ」、「ねぎ入付」、「ふくろいか」、「すし」などの記述が7日まで続く。
ユーモアの持ち主
当時、望東尼は60歳だが、本当に「もち十たべ」たのだろうか。年末の書簡のひとつに「餅を貰ひ候ても、此頃(このころ)のふぐあひにては人にのみ遣(や)り申候」とあるように、体調の悪さを理由に、もらった餅を人にあげていたようだ。せっかくの差し入れを同じ島民に回すと角が立つから、もしかしたら「法師の流されたるが忍びやかに来」(夢)た時に餅をあげていたのかもしれない。この記述から、「もち十たべ」たのであれば、かなり小さい餅だったか。
ちなみに「人にのみ」やったというのは、『夢かぞへ』に、「夜毎に鼠(ねずみ)の騒がし」いので自分の食べ物を残して「夜々(よよ)に遣(やり)しゝ」「今宵は遣す時に、(大人しくするよう)くれゞ(ぐれ)言ひきか」せたら「騒がずなり」だったことが記されており、これを受けた書き方をしているものと思われる。
この時読んだ歌に
「事分きて言へば鼠も知り顔に騒がずなるは人にまされり」
というのがあるが、望東尼はかなりのユーモアの持ち主であったようだ。
島民の優しさの味
望東尼の文章にはどこか諧謔性(かいぎゃくせい)(=ユーモア)があり、そこに彼女の人柄を強く感じる。だからこそ皆がその人間性に魅かれるところがあったのだろう。島民との交流や役人の計らい、手紙や著述の内容にそのことが如実に表れているような気がするのである。
望東尼が食べた雑煮の味は、まぎれもなく島民の優しさであり、獄中において心細い彼女の気を和ませるに十分であったに違いない。
個人的になるが、記述の具材で彼女が食べたであろう雑煮が再現できたなら、ぜひ食してみたい希望を述べて筆を置く。
注1)文中読み下し文は『「野村望東尼全集」佐々木信綱編 野村望東尼全集刊行會 昭和三十三年』に倣った。
(糸島市志摩 河村裕一郎)糸島新聞・2023年1月1日付
望東尼の雑煮を再現/料理研究家の佐藤さん
野村望東尼が食べたであろう姫島の雑煮を、糸島を拠点に活躍する料理研究家の佐藤彰子さんに再現してもらった=レシピ参照。佐藤さんは祖父が姫島の漁師だったこともあり、「アワビが入るのが姫島っぽい。魚介のうまみが利いただしは上品で、彩りも考えられている」と感心しきり。
「あまり汁物に入れない山芋も、とろみをつけ、寒い時期にあつあつの雑煮が食べられるように考えたのかも。当時の姫島の人たちの、望東尼への心遣いが伝わってきますね」と話していた。

姫島の雑煮レシピ
□材料(2人分)
寒ブリ(上身)60g
アワビ1個
シイタケ(戻)2枚
京菜(水菜またはかつお菜)1束
里芋1個
ゴボウ(薄切り)8枚
ニンジン(輪切り)4枚
山芋(いちょう切り)4枚
するめ(1㎝角)10g
丸餅4個
だし汁3カップ
A(うま口醬油(しょうゆ)大さじ2)


□作り方
①寒ブリは塩をして一晩おき、一人一切れ食べやすく切って茹(ゆ)でる。アワビは殻を外しヒモと口を取り除き薄 切りにする。
②干しシイタケは一晩水に戻して柔らかくし、石突を切って薄切りにする。水菜はきれいに洗って色よく茹で、4~5㎝の長さに切る。里芋は皮をこそげ、塩でもんでぬめりを取って縦半分に切り、ゴボウは洗って斜め薄切り、ニンジンは5㎜厚の輪切りにし、柔らかく茹でる。山芋は皮をむいていちょう切りにする。
③だし用に一晩つけておいたコンブを敷き、丸餅を並べ、水を入れて柔らかく茹でる。
④鍋にだし3カップを入れAで味をつけ、①と、水菜以外の②を入れて温める。⑤お椀に③の餅、④を入れて形よく盛り、だし汁をはる。
雑煮だしの取り方
□材料
煮干し30g、コンブ10g、干しシイタケ4枚、水4カップ
□作り方
ボールに分量の水・煮干し・コンブ・干しシイタケを入れ一晩水につける。
一晩つけた②の干しシイタケの戻し汁も固く絞った濡れ布巾でこす。
煮干しを入れない家も多い。出汁を沸騰させてとることもある。