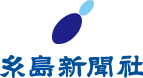9月16日の没後100年が迫り、その生き方に関心が集まる伊藤野枝。本紙でも今週号で、福岡市総合図書館で開催中のトピック展示を取り上げ、野枝の生涯を追った。展示を見ていると、野枝自身の言葉に触れてみたいとの思いに駆られ、野枝の創作や評論、書簡を収録した「伊藤野枝集」(森まゆみ編、岩波文庫)を紐解いてみた▼冒頭に登場するのが七五調の叙情的な詩「東の渚(なぎさ)」だ。書き出しは「東の磯の離れ岩、/その褐色の岩の背に、/今日もとまったケエツブロウよ、/何故にお前はそのように/かなしい声してお泣きやる。」(/は改行)。17歳の野枝の雑誌「青鞜(せいとう)」デビュー作だ▼故郷の旧今宿村の海辺が舞台だが、日暮れの海は野枝に悲しみを募らせるばかり。「ねえケエツブロウやいっその事に/死んでおしまい!その岩の上でー/お前が死ねば私も死ぬよ/どうせ死ぬならケエツブロウよ/かなしお前とあの渦巻へー」。ケエツブロウとは海鳥のこと。野枝は海鳥に自分を重ね、追い詰められていた気持ちをぶちまけた▼この詩の発表前、野枝は家同士で決めた婚姻を拒否し、故郷で離婚交渉に臨んだ。だが、旧態依然とした家族制度は、自由に恋愛して生きることを許さなかった。娘は家の繁栄のため、親の都合によって結婚するのが当然と考えられていた時代だった▼ただ、野枝は絶望の淵からはい上がった。詩の最後にある「どうせ死ぬなら」には、諦めではなく、社会を変えていく強烈な決意を込めているのではないか。理不尽な因習が渦巻く社会に飛び込み、打破してしまえー。窮地に押しつぶされそうになるたびに、力強く立ち上がった野枝の姿が思い浮かぶ。
コラム まち角