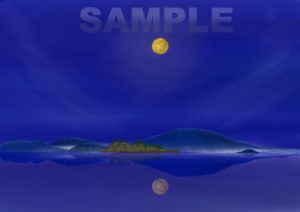「行きたい、居たい、やってみたい」子ども主体の居場所・遊び場
近年、子どもたちが思い切り体を動かして遊べる場所が少なくなっています。地域の結びつきが希薄になり、少子化の影響で子どもや若者が一緒に成長し、学び合える機会も減っています。代わりにスマートフォンやゲームなどのネット空間が遊び場となり、自分の身体を動かして体感する時間も短くなっています。しかし、そんな状況を変えようと、子どもたちのために居場所や遊び場をつくっている人たちがいます。現在の子どもたちがなかなか経験できないことができる場や、地域の人々と関わり合える場を、ママトコラボ取材班が直接取材しました。子どもたち自身が「行きたい・居たい・やってみたい」と思える場所です。
自分のペースで過ごす
NPO法人いとしま児童クラブ「みんなの居場所」
前原中学校から北東へ約200メートル。小高い住宅地にカラフルに描かれたブロック塀の一軒家がある。NPO法人いとしま児童クラブの「みんなの居場所」だ。平日10時から18時、予約不要で誰でも無料で利用できる。小学生が多いが、中高生、未就学児、保護者も来所し、3~4人ほどのスタッフが見守る。

ここでは何をしても良い。読書、ゲーム、おしゃべり、工作、勉強、外遊び。ボーっとするのも昼寝もOK。「子どものしたいことをできるだけかなえたい。だから、てんやわんやの時もある。この前は、階段に毛糸を張り巡らし、大きなクモの巣を作っていたっけ」と笑うのは同クラブ事務局長の吉川貴子さん。「『将来のために』と頑張り過ぎ、疲れ果てている子どもたちがいる。まずは『今』元気でいてほしい。そうすれば、子どもは自ずと未来に向かって動き出す。大事なのは今。今の積み重ねに未来がある」と語る。


「私にとってここは天国だよ。友達がいるし、家だと妹がうるさいからさ」と口をとがらせて見せる9歳の女の子。ここで新たな友達ができたとか。ある保護者からは「息子が学校に行かなくてもここで目を掛けてもらえるから、自分に少し余裕ができる。相談もできるからありがたい」との声。「誰かの気配がある中で、自分のペースで過ごせる。そんなホッとできる居場所であれたら」と吉川さんは願う。 (吉川 美咲)
問い合わせ=092(332)0112
ホームページ=https://itoshima-jidoclub.com/
人の温かさに触れ合う
子育て交流サロンいとキッズ
「子育て交流サロンいとキッズ」は、怡土校区社会福祉協議会が20年以上運営を続ける子育てサロン。校区内外の未就園児とその保護者を対象に月2回開催している。
3代目代表の中村寿子さんは、保育士で市の子育て支援センターの初代センター長を務めた保育の大ベテラン。「参加者、スタッフ、地域をつなぎたい」との思いで活動に尽力する。

取材の日、怡土コミュニティセンターの一室は8組の親子でにぎわっていた。「わあ、上手」とのスタッフの声に、女の子がおもちゃを手ににっこりと歯を見せる。1歳の男の子は母親の膝に座り、和やかにおしゃべりを楽しむ母たちの顔を交互に見ていた。「子どもは人の温かさに触れて育つことが大切。大人同士が笑顔でつながることで、子どもに安心感と笑顔が生まれますね」と中村さん。

校区の少子高齢化が進み住民同士の交流も減る中、外に出て地域と触れ合う体験も多く取り入れる。地元の人と協力して行う芋掘りや焼き芋会、ミカン狩り、イチゴ摘みは参加者に大好評。同時に「地域の皆で取り組んでいる」と感じることが自身の励みにもなるという。
過去の参加者の中には、育児が一段落し場をつくる側の活動を始めた母親も。「人と触れ合うことの大切さを感じ取ってもらいたい」という中村さんの思いと活動は、着実に次の世代へと受け継がれている。 (榮 鮎子)

毎月第1、第3木曜日10時~11時半
怡土コミュニティセンター和室
問い合わせ(中村さん)=090(9076)7645
自由に遊べる環境を作る
いとしまの遊び場ったい!
6月4日、糸島市健康福祉センターあごらのゲートボール場で「いとしまの遊び場ったい!」が主催するプレーパークが開催された。プレーパークは、子どもたちが自由に遊びを見つける場だ。人や物を傷つける危険な行為以外に大人が口出しすることはなく、縄跳びやボール遊びに加えて普段できないたき火や木工遊びなども体験できる。

この日はボランティアのスタッフ5人が見守る中、10カ月の赤ちゃんから小学生の子ども十数人が参加し、さまざまな遊びをした。たき火でべっ甲飴(あめ)を作った1年生の女の子は「形をきれいにするときに、くるくるするのが難しかったけどおいしかった」と初めての体験に笑顔を見せた。木工遊びではのこぎりや金づちを使い、子どもたちが協力してロボットを作る様子も見られた。プレーパークは、年齢の違う子どもたちが道具の使い方や遊びのルールを教え合い、関わりを持てる場でもある。

代表の奥村亮介さん(35)は「子どもたちが教えあう姿はほほえましい。同じ子がまた遊びに来てくれるとやって良かったと思う」とやりがいを語った。「子どもたちの居場所がなくならないように」という思いで活動を続けている奥村さん。「いろんな規制が増える現状だけど、できるだけ自由に遊べる場をつくっていきたい」と今後の意欲を見せた。 (朱雀 亜唯美)

月1回開催。
詳細はホームページ=https://itoshima-asobiba.jimdofree.com/
親子ともに刺激の場に
ひよこクラブ
「ひよこクラブ」は、毎週水曜日に活動する子育てサークル。0歳~3歳の子どもとその保護者がメンバーで、現在は10組の親子が所属している。毎週の活動内容は、毎月2人の保護者が担当し、屋内での遊びや制作、屋外での花見や乗馬など多様だ。

拠点の可也コミュニティセンター大研修室は定員120人の板の間。子どもたちは自由に動き回り、泣いても大きな声を出しても他人の目は気にならない。7カ月の双子と参加する福森那奈さんは、「いとハピで教えてもらいました。毎週定期的に活動する親子サークルで見つけられたのは、ここだけでした。来ると息抜きになります」と話す。福森さんの横では、参加する別の母親が双子を抱き、2歳の女の子も赤ちゃんをあやしていた。

今年の代表を務める田中宥朱(ゆみ)さんは「今いる子どもたちはコロナ禍に産まれ、家族以外とのふれあいがほとんどなかった子もいます。ひよこクラブは子どもにもママにも刺激になる場です」とこの場が果たす役割を教えてくれた。
「初期メンバーはもういませんが、30年以上続いています。必要とする人が常にいるからかな」と話す田中さんの長女も来年は幼稚園に入園する。メンバーは入れ替わるが、ひよこクラブが母親にとって必要な場であることは変わらない。取材中、一度も怒る母親がいないことが印象的だった。 (南 明日香)

毎週水曜日10時半~正午。
連絡先のメールアドレス=hiyokoclub.itoshima@gmail.com
食事、農業、学習を体験
寺子屋しましま
糸島市志摩小金丸にある「寺子屋しましま」では「食育」「農業」「学習」を活動の三本柱とし、トレーラーハウスを使った子どもの居場所で、学びと食事を提供する。毎週土曜日に開催し参加費は無料だ。
取材日は代表の阪井麻紀さん(50)を中心に西南学院大学教員の伊東未来(みく)さん(42)、九大生ボランティアら5人のスタッフと、小学生から中学生までの6人が参加。午前中は九大生による学習支援、昼食後は野菜の飾り切りやニンニクの収穫体験などに取り組んだ。

「味覚が敏感なうちに本物の味を知ってほしい」と食事では無添加食品を使用しており、飼育しているニワトリの卵で、卵焼きや茶わん蒸しなどを子どもたちと一緒に調理することもある。実体験からの学びを大切にしている阪井さんは、この春にチャボを卵からふ化させた。殻からくちばしだけを出しピーピー鳴いているヒナに、子どもたちと一緒に「頑張れー」と応援。「みんなも同じように、応援されて生まれてきたとよ」と伝えたそうだ。

これから子どもたちは、どんどん外の世界へ進んでいく。「いろんな子どもに、こういう所もあるんだと知ってもらい、困った時に思い出して戻って来られる場所にしていきたい」と阪井さんは語った。 (村上 和世)

毎週土曜日10時半~15時
連絡先=080(3979)2964
メールアドレス=info@terracoya.net
ホームページ=https://terracoya.net/
常に寄り添う見守り隊
伊藤吉己さん宅
約12年前から一貴山見守り隊として子どもたちを見守る伊藤吉己さん(72)。下校した小学生たちが、週に2、3日ほど二丈武にある伊藤さん宅に集まり、宿題をしたり、友達とおしゃべりをしたり、思い思いの時間を過ごしている。「朝の登校時に『今日行ってもいい?』って子どもたちが聞いてくるんです」と笑顔で話す伊藤さん。

10年ほど前に近所の子どもたちに魚釣りを教えたことがきっかけで、子どもたちが家によく遊びに来るようになった。「子どもたちの集まる場をつくろうと思っていたのではなくて、気づいたら集まる場になっていた」と懐かしそうに当時を振り返る。

初めて遊びに来た子も「伊藤さん!」と慣れた様子で呼び、のびのびと過ごしているのは、伊藤さんが見守り隊で毎朝子どもたちの登校に付き添い、お互い慣れ親しんでいるから。おもちゃなど遊び道具がなくても、走り回ったり、かくれんぼをしたり、元気いっぱいの子どもたちを「子どもは遊びの天才。何もなくても自分たちで遊びを考える」と温かく見守る。

高学年になると、時には自分の話を聞いてほしい子もおり、そんな時は口を挟まず、ただ耳を傾ける。「子どもは話すだけでも安心する。聞いてくれる人がいるだけでいい」。子どもたちに寄り添う伊藤さんが一番大切にしていることだ。 (柳詰 紘子)