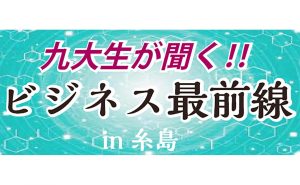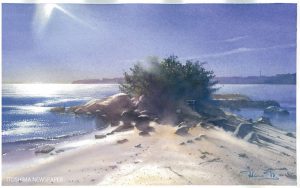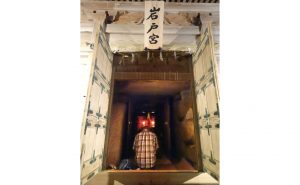関東大震災と野枝一家
「天変地異が起りさうだ」。1923(大正12)年8月、作家芥川龍之介は、そう会う人ごとに言いました。その年、真夏にも関わらず、なぜか藤や山吹などの花が乱れ咲いているのを見て芥川はそう言ったのでした(「大震雑記」)。
「関東大震災」は、その芥川の予言からまもない9月1日におこりました。かつてない大地震は都市を破壊し、多くの人から大切な命を奪い、また、かろうじて生き延びた人々の運命までも大きく狂わせることになりました。
地震が発生した午前11時58分、婦人解放運動家で文筆家の伊藤野枝夫妻は自宅で、長女魔子は遊びに出かけた歌人でジャーナリストの安成二郎宅で罹災(りさい)しました。父親の大杉栄は、地震がくるやいなや「尻っぱしょり」で安成宅までかけつけ、怯(おび)える魔子を連れ戻しました。
各地で甚大な被害があったにもかかわらず、幸いなことに、野枝の自宅は少し壁が落ちただけでした。野枝はすぐに叔父の代準介に手紙をだします。「未曾有の大地震で東京はひっくりかえるような騒ぎです。しかし私どもは一家中無事ですからご安心下さい。」(同年9月3日)と書き、災害による食糧難のため白米を送るようお願いしています。
これまで経験したことのない大災害に、世の中は不安定になっていました。あらゆる流言飛語が飛び交い、誰もが疲弊していました。そのようななかでも一家は日常を取り戻そうとしていました。運動がてら子ども達を乳母車に乗せ近所を散歩したり、毎晩夜警をする大杉の姿がありました。こうした様子に、「主義者狩り」を心配して作家内田魯庵は忠告をしましたが、大杉は笑って受け流しました。
同月16日、野枝夫妻は横浜の避難先にいる大杉の弟、勇一家のもとへとかけつけます。いつもなら一緒に連れていく魔子は、遊びに夢中で残ることとなりました。勇夫婦と会い、無事を喜んだ野枝夫妻は、勇宅にいた大杉の妹橘あやめの一人息子宗一を連れて帰京します。思いがけない天災に、着るものにも不自由していた宗一は、「女の子の浴衣」を着ていました。ともに歩く宗一の姿は、魔子のようにもみえたかもしれません。
その日の夕刻、3人が横浜から自宅近くまで戻ったとき、ふいに軍靴の音が響きました。そして、その音とともに、3人の姿はふっつりと消えてしまったのです。
この不測の事態を最初に気づいたのは、18日、横浜から衣類をもらいに訪れた勇夫妻でした。また同日「報知新聞」夕刊に大杉らが拘束され、麹町憲兵分隊に留置されたことが報道されました。しかし、勇が問い合わせるも門前払いばかり、3人の行方はようとしてわかりませんでした。
ようやく事件が明るみになったのは24日のこと。「大杉栄外二名を致死」と陸軍省より正式発表されたのです。あの日、野枝夫妻と宗一は、憲兵大尉甘粕正彦らによって拘束、麹町憲兵分隊に連行され、その夜、別々の個室での尋問ののち、激しい暴行をうけ非業の死を遂げたことが、ついに明らかになったのでした。
(福岡市総合図書館文学・映像課 特別資料専門員 神谷優子)(文中敬称略)=毎月1回掲載
●参考 ▽井手文子・堀切利高編『定本伊藤野枝全集』学藝書林(2000)▽大杉豊編著『日録・大杉栄伝』社会評論社(2009)▽冨板敦『大杉栄年譜』ぱる出版(2022)▽児玉千尋『文豪たちの関東大震災』皓星社(2023)