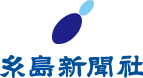前田美代子さんの児童書「風になるまで」
子供の目を通し 平和問いかける
子どもの視点から雷山空襲の悲惨さを描き、今に平和を問いかけている本がある。児童書「風になるまで」(石風社)。筆者は、糸島市雷山で育った福岡市南区の前田美代子さん(83)。米軍の爆撃により8人が犠牲になった空襲の日、空にはきれいな月が輝いていたという、のどかな里に襲いかかった悲劇を親戚から聞いて衝撃を受けた。「ふるさと雷山の忘れがたい記憶とともに書きとどめたい」と筆をとった。

創作の舞台は、戦後から10年経った福岡近郊の村。自然豊かな地で暮らす少年少女が、村の墓地近くにある「鬼ぐら」(ほら穴)で出会ったのは、10年前に焼夷弾の爆撃で死んでしまった子どもたち。語られるのは、空襲の日に目にした光景、恐ろしい体験…。あの日から時が止まったままになっている彼らが「風になるまで」の交流を描いている。
前田さんは終戦後に満州から引き揚げ、雷山で暮らし始めたのは5歳のころ。直接雷山空襲を経験しておらず、空襲のことを少し耳にすることはあっても、詳しく知る機会はなかったという。「あまりみんな語りませんでしたよ。(つらい経験を)話したくなかったんでしょうね」。
子どものころから文章を書くことが好きだった前田さん。雷山を舞台にした小説の構想を考えていた約24年前、親戚にあたる吉村智子さん(旧姓:井手)とその夫、義男さんとで話すことがあった。智子さんは空襲で両親と姉を亡くし、義男さんも当時、福吉村(現在の糸島市二丈大入)に暮らしていた。話が雷山空襲におよんだ時、義男さんはふと「(空襲の日は)月がきれいだった」とつぶやいた。その言葉を聞いた時、平穏さを突如として惨劇に変えてしまう戦争の恐ろしさに震えが走った。
この頃、雷山空襲の記録集「村に火の雨が…」(「雷山空襲を記録する会」編)が出版され、前田さんは被災者の生々しい証言を読んだばかりだった。
「本でも『月の明るい夜だった』と何人かの方が証言していました。月は高いところから空襲のすべてを見ていた、と自分の中でイメージが膨み、目が潤んできて…。どうしてもその情景を書きたいと思いました」。
作中で鬼ぐらの子どもたちは、空襲の夜に輝いていた月が、水田に映っていた様子を回想する。「月の涙が水面(みなも)に渡ってさざ波をたてていた。泣き続けてたんだね、きっと」。水田の月の揺らめきを、生きたくても生きられなった人、夢を抱く前に死んでいった子どもたちの悲しみとして描いた。
「風になるまで」を自費出版したのは2005年。前田さんは「今も世界のあちらこちらで戦争が起こっている。炎を見るたびに嫌です」と言い「やはり、戦争はあってはならない」と強く語る。
本のあとがきには、子どもたちに向け、こう記した。「私は、微力な抵抗をこの物語にこめました。戦争のない、希望に満ちた未来をあなたたちに残したくて」。
イラストは、糸島高出身のいのうえしんぢさん。