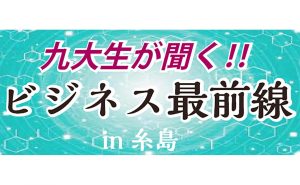避難の備えこそ肝心
能登半島地震から間もなく半年。現地の対策本部長として災害復旧の陣頭指揮を執ってきた内閣府副大臣(防災など担当)の古賀篤氏が、糸島新聞のインタビューに答え、大きな災害に備え、避難生活を想定した準備の大切さを強調した。

-災害時の被害を軽減するために必要な対策として自助・共助・公助の三つがある。初動対応のとき、これらの取り組みがどうだったのか、感じたことは。
国は発生日の元日から(必要性の高いものを送る)プッシュ支援に取り掛かり、金沢市に設けた拠点に物資が運ばれてくるが、被災地までの道のりは遠く、道路は寸断されている。食料品の提供があっても、現地に届くまでにはさらに1、2日はかかる。そこから、避難所にいる方もいれば、ご自宅にいる方もいるので、配るのに時間がかかる。
ということは、3日分くらいは自分で非常食を用意しておかないと、食事ができないことになる。後日、1日1回しか届かないパンを、家族で分け合って食べていたと聞いて、大変なご苦労をされていたことが分かった。
やはり大切なのは自助。輪島市を中心に火災が起こったが、110番、119番が一斉に鳴っても救助に行けない。消防の方からも「全部は電話を取れなかった」という話を聞いた。いざというときは自助か共助。数日間は、自分で身を守るか、周りの人と助け合うしかない。そこから県と国が救助に来るということになる。
災害はいつ発生するか分からない。自宅の防災グッズや非常食は十分か、どこに逃げるのかを家族で話し合ってほしい。3年前に災害対策基本法が改正されて、個別の避難計画を作ることが自治体の努力義務になっているが、特にご高齢の方や障がい者の方々とか、どうしても周りの人の助けがいる方は避難計画を作っておいて、どこに避難するのか、助けてくれる人は誰か、確認しておく必要があるというのが、今回の地震からすごく感じたところ。
集落の孤立化対策急務
-いまだ、いざという時は公助に頼ればいいという人もいると思うが、意識を変えるにはどうすればいいか。
大きな災害が発生して、避難先では少なくとも数日はこんな生活を送るんだということを少しでも体験すると、「確かに、なんかあったら大変だ」って、実感してもらうきっかけになると思う。だから訓練の幅を、発災直後だけではなくて、その数日後まで想定して実施した方がいい。
あと、水の問題もある。あまりに蛇口から水が出ることが普通になっているが、特に今回の地震がそうだったが、能登半島ではいまだに水が出ない地域が少なからずある。そうすると困るのがトイレ。次に風呂。その次に洗濯。あと、病院での透析にも大量の水が必要。石川では貯水タンクが壊れて透析ができなくなった病院があって、患者さんを(被害の少ない)県南に運んだケースがあった。今後は、糸島にもあると思うが、生活用水を確保するために防災井戸を活用することなどが、極めて大事になる。
-石川では孤立集落が問題になったが、糸島でも起こりえるか。
石川では道路が寸断されて、バイクとか徒歩でなら何とかたどり着けるということが発生したが、それは能登半島特有の問題ではなく、糸島でも起こりうる。その時はヘリで空から行くしかないので、空からの救助についてももう少ししっかり考えた方がいいのではないか。自衛隊が一番大きなヘリを持っているので、石川では消防も警察も、自衛隊のヘリに資機材を運んでもらっているが、その時に「じゃあ機材は載りますか」という話になる。いざヘリに機材を載せようというときに、大きすぎて入らないのでは話にならない。消防は過去の反省を踏まえて、(自衛隊のヘリに積載できるよう)機材のサイズを調整していたと聞いた。関係機関も、機材が積載可能か、サイズをチェックしなければならない。
仮設住宅対応を柔軟に
-避難先についての課題は。
石川では、いまも1次避難所におられたり、2次避難所のホテルや旅館や、次のステップに進んで仮設住宅とか、賃貸の「みなし仮設住宅」に入ったり、あるいはご自宅や車中泊も若干おられる。2次避難するということが、命をつなぐ意味では極めて大事。1次避難所では感染の問題だったり、寒さを防いだりするのが難しかったりする。
糸島には2次避難所がどれくらいあるのか、確認しておかないといけない。石川では、金沢市などにたくさんの方が避難されている。糸島で置き換えるなら福岡市なんだろうけど、そこも被害に遭っていたら、どこに避難するのか。いろんなケースを想定し、佐賀に応援を頼むとか、柔軟にいくつかの選択肢を考えておいた方がいい。
-石川の場合、避難所は設けたが、避難したがらない人が多くいたと聞く。
やはり地元から離れたくない、家を片付けたいというのがある。今回の震災では2次避難をする地域が100キロ以上離れる被災地もあった。糸島でいうと、熊本くらい遠い。そうすると、やっぱり避難するのをちゅうちょされる。「自分は地元に戻れるのかな」と、不安を感じるご高齢の方も多い。
2次避難所のホテルや旅館は、本来の観光目的で使われる時期がいつになるのかといった問題や、お父さんだけ被災地に残って仕事を続けて、家族は2次避難所で暮らすといった家族が別れて暮らす場合も多く、いつまでそれぞれ離れて生活するのかといった家族の問題にもなる。
-災害対応マニュアルの必要性については。
国も自治体もそうだが、災害が発生したときの対応は、基本同じだと思っている。インフラを復旧させ、物資を運び、避難所を中心に生活支援をする。それをどういう手順でどういう風に進めていくのか。誰が行ってもしっかりと仕事が果たせるように、マニュアルをより具体的に、手順を追って作っておきたい。
岸田総理にも折に触れて現地の復旧・復興の状況を報告するとともに、今後の震災対応の在り方も相談している。政府の災害対応力をより強化したいと考えており、福岡・糸島における災害対応についても地元の方とご相談しながら進めていきたい。
◇
古賀氏は昨年12月に内閣府副大臣に就任。1月1日深夜に自衛隊ヘリで石川県入りし、県庁に設置した対策本部で、内閣府など最大約300人の国の職員とともに人命救助や水道などライフラインの復旧、被災地への支援物資の輸送、避難所での生活支援に当たった。
石川県の非常災害対策本部会議にも出席し、県や被災自治体との情報共有、国の関係省庁や首相官邸との連絡調整役を担った。
また輪島市など被災地に足を運び、自らの目で状況を把握。輪島塗などの伝統産業や温泉などの観光業、学校や保育園、のと鉄道などの公共交通機関の視察を行い、関係者の声に耳を傾けた。
古賀氏は、糸島の人たちに「皆さんからたくさんの義援金をいただき、大変にありがたい。石川はまだ復興復旧の緒についたばかり。もう少し落ち着いたら、観光で訪れていただくとか、引き続き石川を応援いただきたい」と語った。