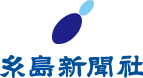いつか、じっくりと向き合ってみようと思っていた油彩画の連作を鑑賞することができた。山口県の実家に帰省していた終戦の日の8月15日、同県立美術館を訪ねた。「没後50年 香月泰男のシベリア・シリーズ」展が開かれていた。57点のシリーズ作品それぞれに、香月の自筆解説文が添えられていた。つづられていたのは、自由を奪い取り、人を死に追いやる戦争とシベリア抑留の壮絶な体験▼同県出身の香月は1942(昭和17)年に召集令状を受け、妻子と別れて旧満州(中国東北部)に動員された。香月が所属した部隊は、日本の無条件降伏後、武装解除を受け、シベリアに送られた。冬は氷点下30度まで下がる極寒の地。そこでの重労働は死と隣り合わせだった▼シリーズは復員後、シベリアをもう一度体験する思いで、生涯描き続けた。その一つが「涅槃(ねはん)」と題された作品。森林伐採を強いられた収容所での食事は、馬のえさにする穀物で作ったおかゆだけという日々。栄養失調と過労により捕虜の1割が死ぬ絶望的な状況だった。香月は死者が出ると、その顔をスケッチした▼「涅槃」の中央には、右脇を下にしてふし、入滅する釈迦の姿。その周りに、手を合わせた幾人もの顔が描かれている。その顔は、香月が収容所でスケッチした死者たちだ。自筆解説文にこうある。「どの顔も美しかった。肉が落ち、目がくぼみ、頬骨だけが突き出た死者の顔は、何か中世絵画のキリストの、デスマスクを思わせるものがあった」▼1年9カ月の抑留生活の後、香月は船で舞鶴港(京都府)に帰ってきた。「復員<タラップ>」。この作品に描かれているのは、故国の大地に降り立つ帰還者たち。だが、その目はどれも何者かが憑依(ひょうい)したように大きく見開いていた。「背中に亡霊を背負っている感じだったかもしれない」(自筆解説文)。収容所で死んだ仲間たちの亡霊が一緒に帰ってきたのかもしれないという。一つ一つの作品に言葉を失うばかりだった。
【糸島市】《糸島新聞連載コラム まち角》