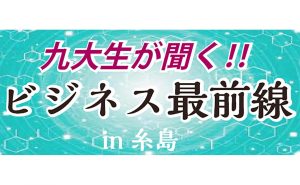24日から全国学校給食週間
食育の日は特別メニュー提供
24日から30日は「全国学校給食週間」。1889年に始まったとされる学校給食。当初は、栄養を補う目的で提供されていたが、現在では児童・生徒が生涯にわたり健康的な生活を送るための「望ましい食習慣」を育む生きた教材としての役割を担う。食への関心を高め、季節の食材を生かし、バランスの取れた献立を提供するために、学校栄養士たちは日々工夫を重ねている。

「今まで嗅いだことがない香りがする」-。昨年12月、糸島市内の小・中学校の給食に、中央アジアにある内陸国ウズベキスタンの伝統料理「プロフ」が登場した。牛肉とニンジンの千切りなどをニンニクと炒め、香辛料のクミンが香る炊き込み風ご飯。初めてのスパイシーな香りに児童たちの驚きの声が響いた。

毎月19日は「食育の日」として、特別なメニューを提供する。本年度のテーマは「和食・日本の郷土料理と世界の料理」とし、各学校の栄養士が手分けして、日本各地や世界の料理を調べ、十分に火を通すなどの衛生管理や時間内に調理できるよう工夫をこらし、献立を考案した。昨年7月は、パリ五輪にちなみ、フランスの伝統料理「ラタトゥイユ」が給食に登場し、五輪の舞台となったフランスの味覚に触れる機会を提供した。
糸島市志摩の引津小では、芥屋地区に伝わる伝統野菜「芥屋かぶ」を育てる活動が行われている。2年生の児童たちは地域住民や糸島農業高校の生徒たちの協力を得て、栽培から収穫、給食での提供までのプロセスを体験した。

昨年12月には、収穫した芥屋かぶを使ったサラダが給食に登場。普段は副菜を残しがちな児童たちも、自分たちで育てたカブをうれしそうに食べた。同校の学校栄養士の中園奈央子さんは「自分たちで育てることで食べ物を大事にする気持ちが芽生えており、貴重な機会となっている」と地域の協力に感謝した。
さまざまな授業や活動に励む児童の様子に「給食時間はほっとする時間になってほしいですね」と中園さん。「毎日楽しみにしてもらえるように」と思いを込め、児童の健やかな成長を願いながら日々の業務に励んでいる。
(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)