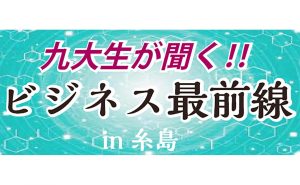鹿児島県の出水平野で冬を過ごしたツルの北帰行が始まった。繁殖地のシベリアや中国東北部を目指す2千~4千キロにもなる長旅。その途中、糸島に姿を見せる群れもあり、田園に降り立って羽を休める。ただ、敵に襲われたのか、ケガをしたツルが見られるときがあるという▼ツルに限らず、どうして多くの種類の鳥たちが命懸けで、南北の移動をするのだろうか。専門家によると、大きな理由は餌のため。シベリアなど北にいる鳥が冬を前にして、餌の多い南へと向かうのはごく自然な行動とみえる。だが、越冬した後、なぜ、再び北へと旅立つのか。そのままとどまっていてもよさそうなものだが、そうしてしまうと、餌の取り合いが激しくなってしまうのだそうだ。むしろ、競争相手の少ないシベリアの方が春と夏には餌を得やすいという▼もう一つ、北に向かうメリットがある。天敵が少ないため、生まれてきたヒナを、より安全に育てられるのだという。冬鳥のクロツラヘラサギの小さな群れが6月になっても今津干潟にいるのを見つけ、保護活動をしている市民団体に問い合わせたことがある。すると、繁殖の年齢に達していない若い鳥の中には、渡りをしない個体がいるとの答えだった。繁殖行動をしないのであれば、あえて危険な渡りはしないのだろう▼より有利な条件で生き、より多くの子孫を残そうと、鳥たちが繰り返してきた渡り。ただ、こうした鳥たちを脅かす事態が起きている。地球温暖化だ。国連の世界気象機関(WMO)は、2年前に発表した気象変動に関する年次報告書の中で、そのことを述べている▼ヨーロッパの117種類の渡り鳥が春に渡ってくる時期がこの50年間で、樹木の芽吹きや昆虫の飛来するときと次第にずれてきているというのだ。それがサハラ以南で越冬する渡り鳥が減少したことの要因と考えられるとしている。温暖化によって、鳥の餌となる昆虫の発生が渡りの時期と合わなくなると、鳥たちは繁殖に必要な餌が十分にとれなくなってしまう。温暖化がもたらす生存の危機。渡り鳥に限ったことではない。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)