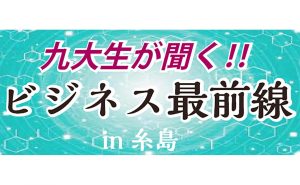新緑の季節、好天に誘われて二丈岳(標高711メートル)登山をした。糸島市二丈福井の加茂ゆらりんこ橋を起点に、二丈渓谷沿いの登山道を登り、小さな盆地になった真名子の地を経て山頂を目指した。息を切らしながら、一人黙々と木漏れ日の差し込む杉木立を歩んでいると、神々しい世界に踏み入れたような気持ちになった▼30年ほど前、スギの原生林が広がる深山で、同じ心境になったことを思い出した。九州で最も高い宮之浦岳(1935メートル)がそびえ「洋上アルプス」と呼ばれる鹿児島県の屋久島。日本初の世界自然遺産に登録されてから間もない頃、登山ガイドに導いてもらい、宮之浦岳から縄文杉、白谷雲水峡へと抜ける縦走コースを歩いた。樹齢数千年という屋久杉の存在をはじめ、森はとてつもない生命力にあふれ、まったくの異世界だった▼登山ガイドの話が、その神秘性をさらに高めた。屋久島には、500年ほど前に始まった「岳参り」と呼ばれる行事があるのだという。集落ごとに崇拝する高峰があり、五穀豊穣(ほうじょう)や豊漁などを願い、集落の代表者が山頂にあるほこらを目指して参拝登山をする。自然の恵みによって生活が営めることに感謝し山の神に祈りを捧げる▼実は、二丈岳でも毎年9月16日、一貴山の集落の人たちが山頂を参拝して神事を行っている。山頂には、麓にある白山神社の祭神、菊理姫命(くくりひめのみこと)をまつるほこらがあり、屋久島の岳参りと通じるところがある▼山に対する信仰には、日本では二つのものがあるという。一つは山を遠くから眺め、山の神を拝む遥拝。もう一つは山中に入って厳しい修行を重ね、悟りの境地を目指す修験。二丈岳登山の後、山と距離をとって遥拝をしてみることにした。数日後、向かったのは糸島半島西端の海辺。唐津湾越しに二丈岳、女岳、浮嶽、十坊山といった脊振山地の山並みが一望できる。峰々は農業に必要な水を里にもたらし、海には川を通して養分を流し込み、海の生態系を豊かにする。二丈岳山頂でしたのと同様、深々と頭を下げ、山の神に手を合わせた。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)