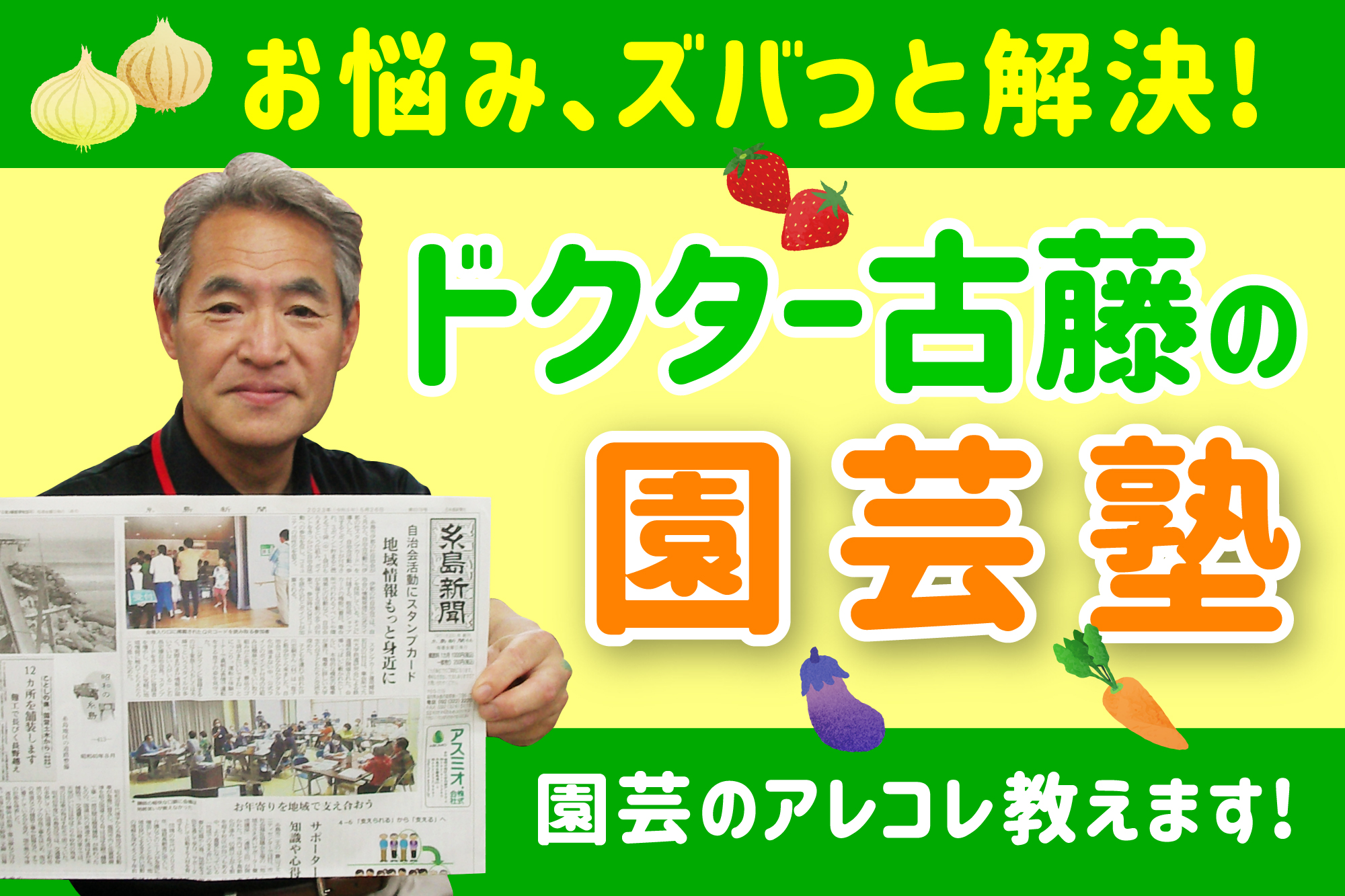プロのナス生産者に聞く
春夏野菜の人気野菜の一つがナス。私が幼少の時から見てきた、ヘビみたいな長い「大長ナス」も栽培されているようですが、現在のトレンドでは、比較的栽培がしやすく、料理の食材として実に幅が広い「中長ナス系」が栽培の主流のようです。
九州では熊本県が断トツに出荷量が多く、次いで福岡県も盛んに栽培されています。熊本県では、有明海に面した玉名市や熊本市西部は平たん地で日照量が多く、土壌も肥沃(ひよく)で、施設(ハウス)を利用した栽培法が中心。逆に高冷地の高森町や、地形的に寒暖差のあるのが特徴の山鹿市鹿本町などは、栽培に適した大長ナスの一大産地となっています。

いざ、家庭菜園に目を向けてみると「あんまり収穫できん」「色の悪~か、色ボケしたとしか収穫できんやった」などと、収量に満足されている方は、多くなさそうです。では、原因はどこにあるのか。
プロのナス生産者に聞いてみました。数ある栽培の要点の中で、菜園者にとって、最も重要な点は何でしょう。インタビュー先は、糸島市のハウスナス生産者、福井浩二さん(72)です。

▼多肥を好み、乾燥を嫌い
特に近年の夏季は高温乾燥状態が続いていますので、そのような状態では、1日に1度はたっぷりと水やりを行い、土壌を潤しておく必要があります。また、いくら固形タイプの肥料を追肥しても、土壌が乾燥した状態では、成分が溶け込にくく、追肥効果の発現が厳しいようです。
そこで、対策として、希釈した市販液体肥料を水に含ませて与えると、早効きのカンフル剤となります。水やりと栄養補給が同時にでき、1週間に1度のペースで与えてください。昔からナスは「水で作れ」と言われるくらいで、水やりは最も重要な点となります。
▼地温を下げる工夫を
いくら、暑さに強いナスでも、日中と夜の寒暖差がない熱帯夜続きの気候では生育がダウンしていきます。そこで、重要なのが根の生育を衰えさせないよう、1度でも構わないので地温を下げる工夫が必要です。
夏の熱射から地温上昇を避けるため、なるべく白っぽい天然素材などを株元などに敷き、強い熱射が反射するようしてみることです。例えば「敷きワラ」「新聞紙(抑えが必要)」など。また、黒マルチを被覆されている方は、マルチの上に不要なアルミホイールを敷いたり、石灰肥料を薄くまき、表面を白っぽくしたりするなどの工夫次第で、地温の上昇を抑制し、コントロールしてくれます。
▼収穫遅れに注意
ナスは、2葉おきに花芽が着花し結実します。よって、採り遅れがないように努めてください。収穫遅れは、株自体の負担を高め、新たな芽吹きや生育を阻害してしまいます。枝葉の混みあった状態では、採光が低下し、病害虫発生率が高くなりますので、枝の切り戻し、摘葉を行い、通気性や採光性を高めてください。
ナスは、うまく育てることで、10月、長ければ11月まで収穫が可能です。秋の好天が続き、日夜の寒暖差が広がるほど、ナスは抗酸化物質である「アントシアニン」を蓄え、うまさも増します。
春に定植した小さな苗が生育中、たくさんの養水分を蓄え、枝葉を大きく生育させて、おいしい実をつけるナス。その栽培の魅力を再発見してみていかがですか。
(シンジェンタジャパン・アグロエコシステムテクニカルマネジャー 古藤俊二)
=糸島新聞ホームページに地域密着情報満載
※糸島新聞紙面で、最新の連載記事を掲載しています。