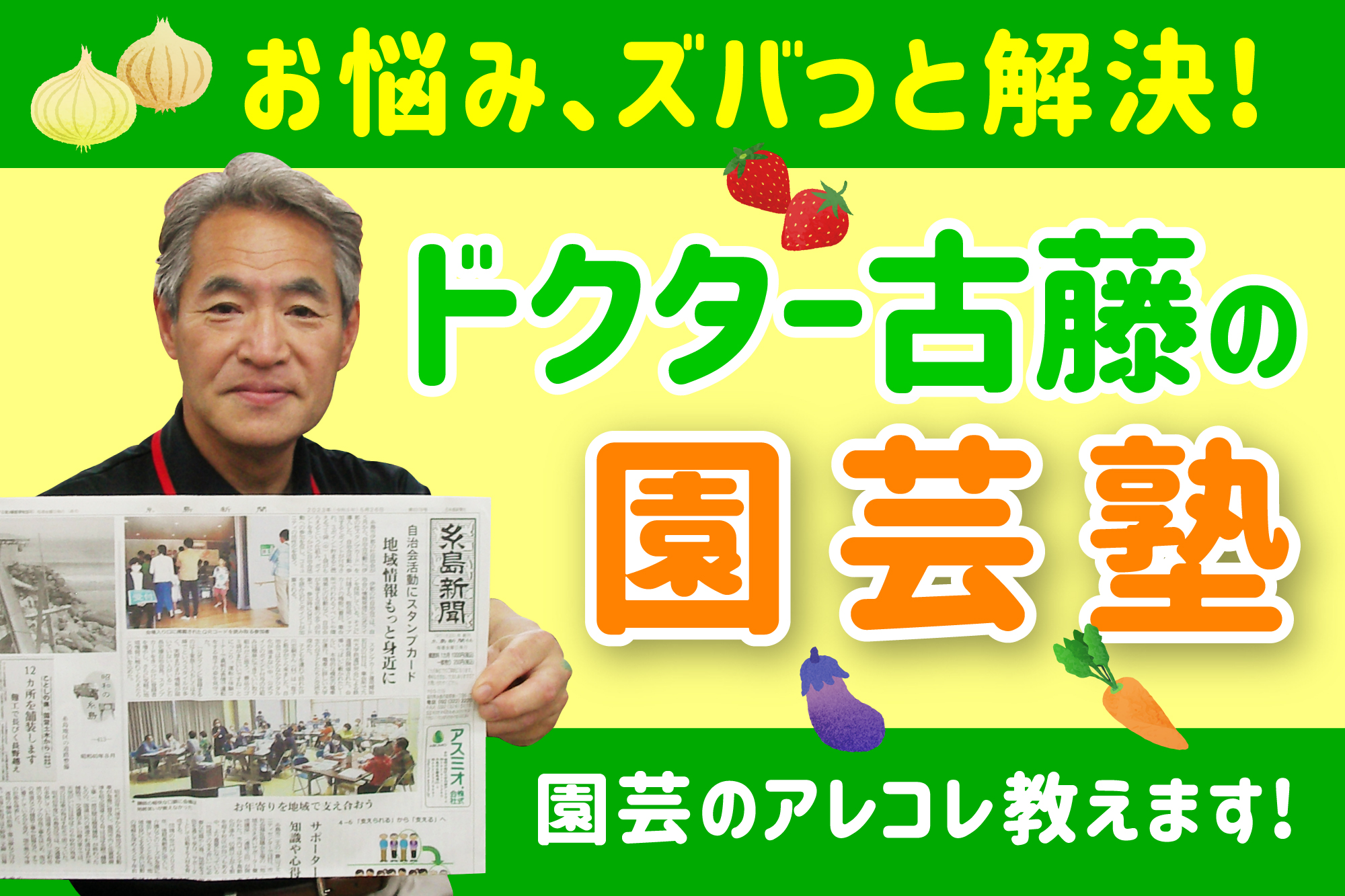高品位の種子を開発し生産 中原採種場
4月下旬の大型連休突入の日曜日、近所のおいちゃんが近場の行楽地のツツジを見に行き、「たまがった~。おおか、おおか。人と車ばっかりやもん」、「自分ちの畑の手入ればしとけばよかった~」と嘆いてありましたね。
皆さんは、GWはどのようにお過ごしでしょうか。5月の野菜栽培も、高い気温を好むオクラにゴーヤ、スイートコーン、インゲン、サツマイモ苗の植え付けと進み、春夏野菜仕込みも後半戦に突入しますが、高品位な種などを提供する各種苗メーカーにとっては、重要なシーズンを迎えています。
種苗の業界では、タキイ種苗やサカタのタネなど、大手総合種苗メーカーの種子を見かけることが多く、全国各地のプロの生産者から家庭菜園の方までに行き届いています。

そんな中で、頑張っているのが福岡市博多区に本社を置く地元の種苗メーカー「中原採種場」さん。各JAや種苗店、園芸店、ホームセンターなど種子を扱う販売店は多くありますが、種の育種や開発研究を行っている企業は、全国でも大手以外ではそう多くありません。

今回、地元で、いろんな品種の種を開発し、供給している中原採種場さんの農場を訪問させていただきました。戦後の食糧難から高度成長期を経て、飽食の時代と言われるまでに豊かな食文化を築き上げてきたわが国、日本。1950年の創業以来、常に食生活の充実をめざすべく新品種の開発と種子の安定供給を目的に活動をされてきました。
環境の整った万全の研究体制を築き、数多くの新しい品種を開発して商品化。日本国内はもとより海外へも広く供給し「ナカハラ・ブランド」のタネとして厚い信頼を寄せられています。
今回、福岡市城南区にある油山研究農場にうかがい、研究開発部長の三小田氏にたいへん興味深く面白いお話を聞くことができました。まず、驚いたのが、生産者などに優秀な野菜の品種の種子を届けるまで、開発になんと約10年かかるとのこと。さらに、その品種が10年後、生産者の手に届く際、その時代のニーズにマッチングしているかが大きなポイントだそうです。

例えば、過去は大きいサイズのハクサイが主流でしたが、現在は、冷蔵庫に収まるミニハクサイが支持されています。これは、スイカも同じですね。昔は大家族で食べる大玉スイカがボリュームもあり、おいしかったのを覚えています。今は、皮が薄くて糖度が高く、味も食感も締まっている小玉や小型のラグビーボール型が人気です。なにしろコンパクトに冷蔵庫に収まるのが利点です。どんなに優秀な品種が開発されても、生産者や消費者から支持されないと種が売れないなど、厳しい面も見えました。
二つ目が気温の変化。年々気温が上昇する傾向の中で、耐暑性の高い品種開発が求められているとのこと。時代が求めても、そう簡単には開発は難しい面もあり、同時に交配を手伝ってくれる昆虫(ミツバチなど)も気温や環境変化(自然環境の減少など)によって、活動範囲が狭まるなどし、育種研究環境も段々厳しくなっているとのことです。
わが国では、遺伝子組み換え作物の商業栽培は行われておらず、農水省が生物多様性の保全や安全性の確保を目的として、監督・指導が行われていますが、一方で世界に目を向けると、広大な栽培面積を誇る米国やブラジル、アルゼンチンなどでは、新たな品種改良技術として「遺伝子組み換え技術(GM)」を取り入れ、乾燥や塩害、病虫害に強い品種などの栽培が進められています。
日頃、食べているいろんな野菜が、中原採種場さんのように、しっかりした施設環境の中で、コツコツと長い年月をかけて交配を何度も繰り返し、優良品種を開発してから生産し、皆様に届いていることを、少しでも知っていただけるとありがたいですね。
(シンジェンタジャパン・アグロエコシステムテクニカルマネジャー 古藤俊二)
=糸島新聞ホームページに地域密着情報満載
※糸島新聞紙面で、最新の連載記事を掲載しています。