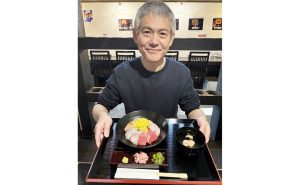収穫間近の黄金色の麦畑と、早植えの水稲の田んぼが糸島の田園地帯で壮大なモザイク模様を描いている。周辺の山並みと大空を映し出す水鏡となった田んぼでは、シラサギがじっとたたずみ、水の中をのぞいている。獲物を狙う姿を見ていると、虫取り網で田んぼの生き物を捕まえ、水槽で飼っていた少年時代を思い出す▼水槽の中の主役はトノサマガエルだった。体長が7センチほどと、アマガエルよりはるかに大きい。緑っぽい背中に白い線が通り、胴には黒いしま模様。どこか悠然として見える様がその名の由来になったそうだ。ただ、トノサマガエルがごく身近な存在だったのは遠い昔のこと▼今の子どもたちがトノサマガエルに出合うことは、探し回らない限りほとんどないだろう。現在は県の希少野生生物のレッドデータブックで「絶滅の危険が増大している種」に選定されているトノサマガエル。見つかると、ニュースとして扱われる時代になった▼本紙では15年前、二丈吉井のため池で、3匹が発見されたという記事を載せている。自然豊かな糸島でも話題となるほど、この頃、すでにトノサマガエルが激減していた。記事は、その要因として、稲の育苗方法が変わり、水をためて苗を育てる水苗代がなくなっていったことを挙げる。流水ではなく、水がたまった場所で産卵するトノサマガエルが、卵を産み付ける場所がなくなったというのだ▼ただ、田んぼの環境は、生き物がすみにくくなる一方というわけではない。本紙の「ドクター古藤の園芸塾」でおなじみの古藤俊二さんによると、田んぼでゲンゴロウを見かけるようになったという。実は、子どものとき、自宅周辺でゲンゴロウを見かけた記憶がない。水中を自在に泳ぎ回る様を目にしたかったが、当時の田んぼは生息に適していなかったのかもしれない。古藤さんによると、殺虫剤・殺菌剤がより環境に配慮して散布されるようになり、姿を消していた生き物が再び見られるようになっている。少年時代のように心躍らせ、あぜ道に踏み入れ、その姿を探してみよう。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)