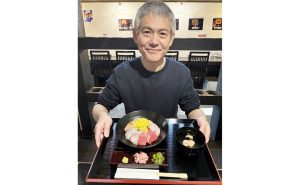かつては、梅雨が終わる頃になると、順調に明けて夏空が続いてくれたらと願ったものだ。天気がぐずついたまま、夏の日差しをまともに浴びることなく、秋になってしまった冷夏の翌年は、その思いがなおさら強かった。それにしても猛暑が常態化する近年、冷夏という言葉は死語になったかのようだ▼「東北では、梅雨明けまでストーブを片付けないよ」。冷夏だった年、仙台で暮らした経験がある知人の話を、興味深く聞いたことがある。東北地方の太平洋沿岸には6~8月ごろ、冷たく湿った風「やませ」が吹き付け、冷害を起こすことがある。稲の出穂や開花の時期に、やませが吹き続けると、凶作となる。やませは「餓死風(がしふう)」と呼ばれ、恐れられてきた▼米価が高騰している「令和の米騒動」。30年ほど前にも「平成の米騒動」が起き、深刻な米不足に見舞われた。なじみのないインディカ米のタイ米が緊急輸入され、売れ残る事態ともなった。この騒動は、やませによる冷害が大きな要因だった。1993年の梅雨から夏にかけ、オホーツク海高気圧の勢力が強く、北から冷たい空気が流れ込んだ。太平洋高気圧が弱かった影響で、六つの台風の上陸もあった▼この年、東北の冷害は特にひどく、宮城県では平年を100とした作況指数が37だった。当時、同県で栽培されていたのは大半がササニシキ。和食に合う食感で人気があったが、冷害に弱く、農家は大打撃をこうむった▼これをきっかけにササニシキの栽培は一気に減った。冷害に強い品種が育成され、ササニシキから切り替えられていった。昔は冷害に対する強さが重視されたが、今は違う。冷夏ではなく猛暑に対して強い品種が求められるようになった。「令和の米騒動」は、供給と需要、在庫の問題が複合的に絡んで起きた。記録的な猛暑で米の品質が低下し供給不足につながっていったのも一因とされる。高温耐性品種が求められる時代。気候変動は主食の生産に大きな影響を及ぼしている。どう対処したらいいのか、一人一人が考え、行動しなければならない。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)