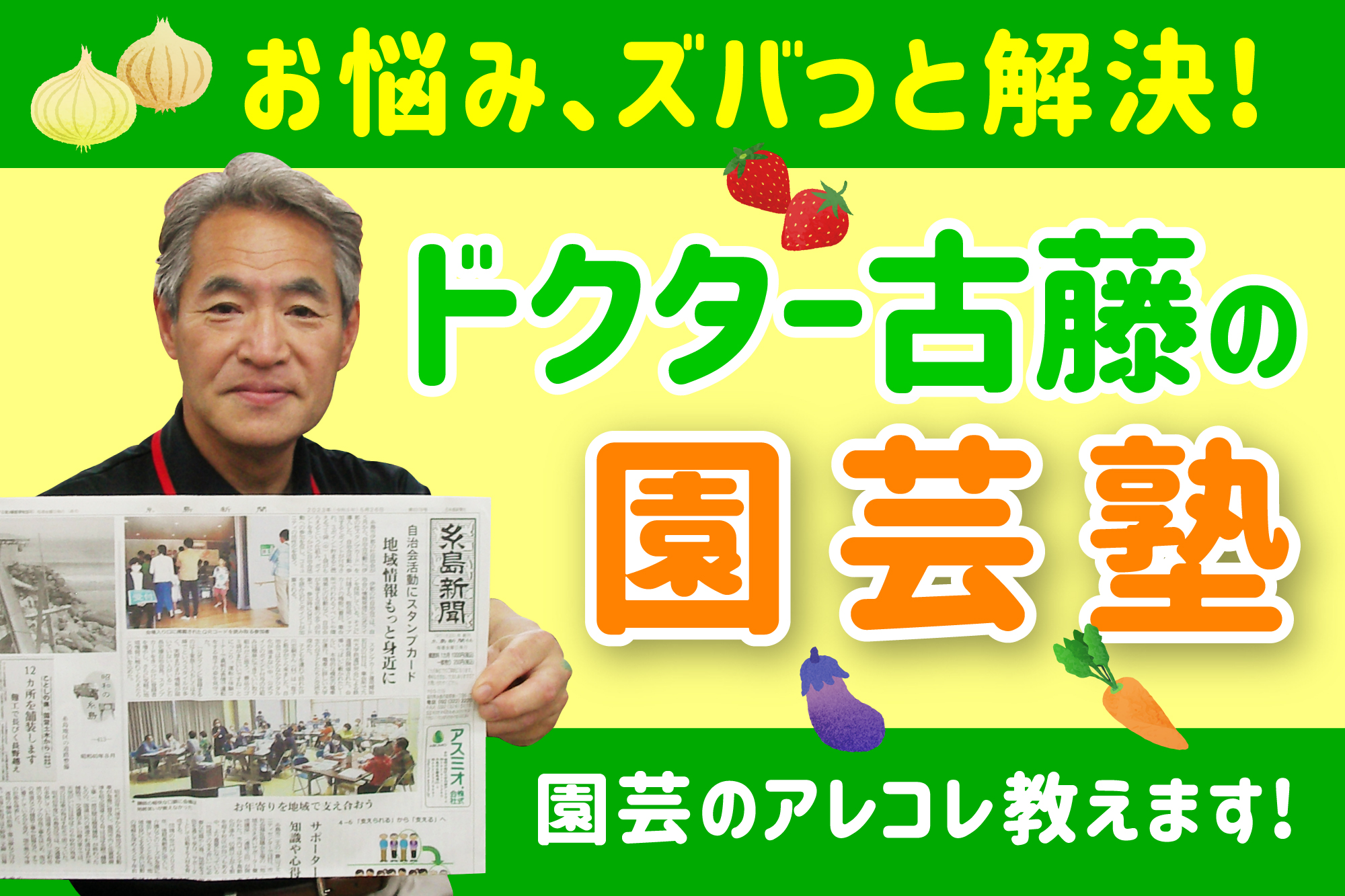沖縄の農業
先月、沖縄県のJAが運営するグリーンセンター(JA糸島ではアグリ)を3日間かけて計25カ所訪問しました。目的は、農業生産現場で起こる問題や課題などのヒアリングを行い、少しでもJAや生産者の方々に技術的な貢献ができないか、現場に足を運びました。

沖縄県の農業は北部、中部、南部と地域よって生産される農畜産物が違っています。北部地域はシークワーサーやタンカン、パイナップルなど果樹が多く栽培され、中部地域は甘藷(かんしょ)、バレイショ、ニンジンなどの根菜類栽培が多く、南部地域は主力のキクをはじめ、インゲン、ピーマン、オクラなど野菜中心の栽培体系です。

本島全体では、やはりサトウキビが圧倒的に栽培されています。宮古島や久米島などでは、島で行われるほとんどの栽培がサトウキビ栽培となっています。
糸満市や名護市など都市近郊では、台風到来が多いためか鉄筋コンクリート造りの住宅の合間に、所狭しとマンゴーやキク栽培のハウスがあり、サトウキビ畑は密集し何か不思議な光景でした。
各JAを回っていると、特に問題になっていたのがウリ科やナス科の果実に被害を与えるセグロウリミバエ。外来種の害虫で、沖縄本島で発見され、農作物へ重大な被害が出る恐れがあるため、県全体で、まん延防止対策がなされ、JAや関係機関はピリピリとされていました。
また、農業者の高齢化は、沖縄県でも急速に進み、離農者も多いとのことです。ただ、新たに移住され、若い新規就農者も多いそうです。
ほぼ一年中温暖な気候で、いろんな作物の栽培ができます。観光ブームでたくさんのおしゃれなホテルが開館し、地元の食材活用の場が増えています。さすが観光と農業の県だなと感心させられました。

その他、スコール(夕立)が多く、温暖であるため、見たこともないような雑草の繁殖ぶり。高い山がないため、ダムに依存した水事情。大型テーマパーク開園を目の前にした道路事情。レンタカーも多く、道路整備が間に合っておらず、私も各所で渋滞に巻き込まれました。
そんな中、一番の課題は、やはり夏季だけでなく発生する慣例化した異常高温、乾燥状況。各作物の生育に大きく影響しています。
「マンゴーの花を交配してくれる有益昆虫が高温で動きが鈍い」「昼夜の気温差が少なくなり、キクの開花が難しくなった」「偏った害虫の発生が多くなり、強くなってきている」など亜熱帯地方の沖縄だからこそ、温暖化の影響は、より深刻かと推測します。
今、私が研究をしている「根の発根力強化」。作物全体の生育の良否を見分けるのは大変難しく、時間も要します。ただ、「いきいきした元気な根が常に作物を支えている」という面を常に追い求めることで、今後さらに問題化するかもしれない高温乾燥や曇天などの生育ストレスに作物が負けないようにすることが、可能かと期待しています。
私たち人間も、熱中症などにならないよう強い体力づくり、免疫力強化が求められています。植物の強い根と同様、我々も足腰を大事にし、今年の夏を乗り切りましょう。
(シンジェンタジャパン・アグロエコシステムテクニカルマネジャー 古藤俊二)
=糸島新聞ホームページに地域密着情報満載
※糸島新聞紙面で、最新の連載記事を掲載しています。