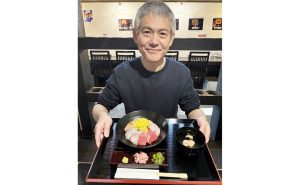自宅の庭に植えている萩(はぎ)が赤紫色の花を咲かせ始めた。何本もの枝先をきれいに垂らした萩は日ごとに華やかさを増し、近いうちに満開となり、美しく彩られた滝のようになるだろう。草冠に秋と書く萩は、まさに秋を代表する草木。奈良時代にできたとされる日本最古の歌集、万葉集の時代には、萩は現代よりもはるかに愛でられていた▼万葉集に収められた山上憶良の歌に「秋の七草」の名を連ねて詠んだ歌があるが、その筆頭に出てくるのは萩。そして、この時代の人々に最も親しまれていた花であることを表しているのが万葉集にある萩を詠んだ歌の数の多さ。元号令和の由来となった「梅花の宴」の梅はこの時代、中国から渡来した珍しい木として、貴族たちが競うようにして邸宅に植えて鑑賞したとされるが、万葉集の歌の数では、萩を詠んだものが20首ほど多く、141首もあって最も数が多い▼「梅花の宴」は、早春に百花のさきがけとして咲く梅の花見。ただ、当時の人たちは花見を春だけのものとはせず秋にも萩で花見を楽しんでいた。その様子を伝える万葉歌がある。「秋風は 涼しくなりぬ 馬並(な)めて いざ野に行かな 芽子(はぎ)の花見に」(作者未詳)。馬に乗って、心を弾ませて萩の咲き誇っている野に出かけていこうとする雰囲気がありありと伝わってくる▼萩はとても生育旺盛で、短くせん定をしても、再び大きく枝を伸ばす。だが、冬になると、地上に出ている茎の部分は枯れてしまう。そして、春になると、地表面近くから新しい芽が出てきて、その様子は「生(は)え木(ぎ)」と呼ばれ、この言葉が萩の名になったとする説もある▼萩は、月見団子やススキと共に、中秋の名月のお供え物にされる。月は豊作を祈願する信仰の対象。ススキは、稲穂が実って垂れる姿に見立てられ、萩はといえば、神様が月見団子を召し上がるとき、箸として使われるのだそうだ。今年の中秋の名月は6日。猛暑を乗り切り、見事に花を咲かせてくれた萩。月の光がその花々を優しく照らし、ねぎらうさまに心を寄せてみたい。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)