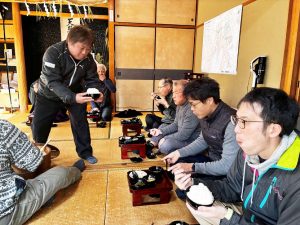この絵のように往生するなら最上の幸せー。九州国立博物館で開催中の特別展「法然(ほうねん)と極楽浄土」で、阿弥陀仏の来迎(らいごう)図と向き合ったとき、自身の臨終もこうあってほしいと思わず願った。描かれているのは、光を放ちながら、雲に乗って極楽浄土から降りて来られる阿弥陀仏の一行。そして、地上にある建物には、その迎えを待つ念仏行者が合掌する姿が描かれている▼浄土宗の開祖、法然は、阿弥陀仏を信じ、ひたすら「南無阿弥陀仏」ととなえると、極楽浄土に往(い)って生まれ変わると説いたという。法然が生きた時代は平安末期から鎌倉初期。繰り返される動乱や、災害、疫病の頻発により、民衆の間には、仏教の教えが衰え、世の中が乱れるという「末法思想」が広がっていた▼「どうにかして救われたい」と、切に願う民衆。しかし、仏教は、難しい教えを理解できたり、それを学ぶ時間があったりする貴族など身分が高い人のためだったという時代が長く続いていた。そこに、専ら念仏をとなえるという、だれでもたやすく実践できる易行(いぎょう)が法然によって説かれた▼身分は関係なく、民衆に救いの手を差し伸べた法然。財がある人は造寺造仏などをして功徳を積むことができたが、貴賤(きせん)による格差が生まれるとして、こうした善事に否定的だったといわれる。だれでも等しく往生できるという法然の教えは多くの民衆に支持された▼特別展では、法然の生涯を描いた絵伝を見ることができる。その中に、末法の世とはどのようなものか、ありありと伝える絵がある。法然は現在の岡山県で生まれ、父親は豪族。法然が9歳の時、父親の屋敷は対立していた武士に夜襲をかけられた。絵には、すさまじい切り合いとなった場面が描かれている。父は深手を負い、亡くなる直前、幼い法然に「敵を恨んではならない」と遺言をしたという。かたき討ちをすれば、恨みによって、また同じ戦いが繰り返されるのだと。法然が出家する導きともなった父親の遺言。万人を救済するという法然の思想に、深いところでつながっているのだと思う。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)