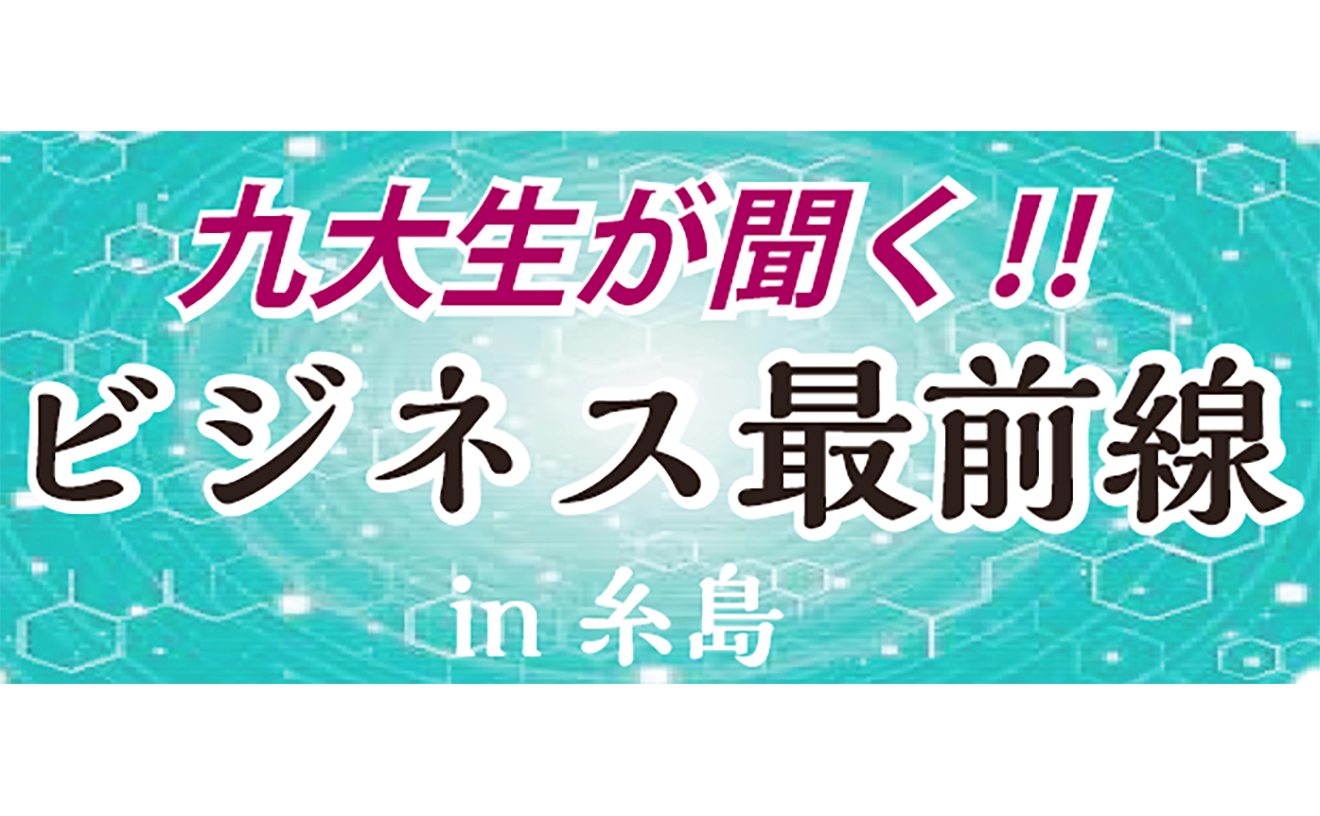株式会社竹次郎㊤ 代表取締役 古賀 貴大さん(38)
このコーナーは、九州大学のインターン生が糸島エリアで事業活動している企業や団体を取材し、その魅力を紹介します。今回は、文学部1年、角田真都が純国産のメンマ作りを通して竹林整備をする株式会社竹次郎の代表取締役、古賀貴大さん(38)を取材しました。

-糸島の野菜や手造りハムなどを使った料理を提供するレストランITOSHIMA(糸島市泊)を経営される一方、2021年からメンマ作りを始められましたね。その経緯を教えてください。
「コロナ禍で飲食の提供がストップし、何か新しいことはできないかと考えたのがメンマ作りのきっかけです。コロナの流行で、飲食店の休業が余儀なくされる中、生産者や配送業者、広告代理店など、さまざまな仕事に影響が出ました。生産者が作ったものが売れないことは一番困った問題だと考え、加工食品を手掛けることにしました。そのとき、メンマ作りに出合いました」
-メンマの原料は、伸び始めた若い竹の『幼竹』と聞いています。その収穫は竹林整備につながり、社会活動とも言えますね。
「竹は繁殖力が非常に強く、1本でも残しておくと次々に新しい竹が生えてきます。竹林を放置すると、成長した竹が倒れます。踏み入れるのが困難になった竹林はイノシシなどの害獣のすみかとなる恐れもあります」
-竹は土砂崩れの原因にもなるそうですね。
「竹の根は浅く、横方向に広がるため、地盤が弱くなるんです。また、竹の急速な繁殖によって他の作物が枯れてしまうこともあります。竹は成長が早く、高く伸びるため、周囲の植物に日光が届かなくなり、結果として枯れてしまうのです」
-竹の需要が減り、放置されている竹林が多いというのが現状ですね。
「昔は日本産のタケノコが広く食べられていました。しかし、中国産タケノコの輸入が始まると、価格競争の影響で国産タケノコの需要が減少し、次第に売れなくなっていきました。採算が取れなくなったことで、後継者も減っていき、竹林の管理が行き届かなくなっていきました」
-かつては竹細工などの工芸品も多く作られていたそうですね。
「プラスチック製品の普及により需要が減り、竹の利用機会が失われていきました。こうしたことから、竹の需要が低下し、それに伴い竹林が放置されるようになったのです。しかし、幼竹を再び食材として活用することで、放置された竹林の整備を進めることができます」
-収穫から加工までの流れを教えてください。
「2~3メートルに成長した幼竹を収穫しています。タケノコとは異なり、掘り起こす必要はなく、根元を切って収穫します。幼竹は簡単に切れるため、子どもや力の弱い方でも作業できます。収穫した幼竹は工場に運び、大まかに切り分けた後、湯がきます。次に、漬物のように塩漬けにし、重石を載せて常温で保存します。その後、漬けた幼竹を機械でカットし、塩抜きの工程に入ります。塩分が多いため、3日間かけてじっくりと塩を抜いていきます。この状態まで加工すれば、1年間常温で保存することが可能になります。幼竹は春にしか収穫できないため、春のうちに塩抜きまで終えたメンマを大量に作り、それを1年通して加工できるようにします」

次回はメンマ作りに対する思いについて深堀していきます。
(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)