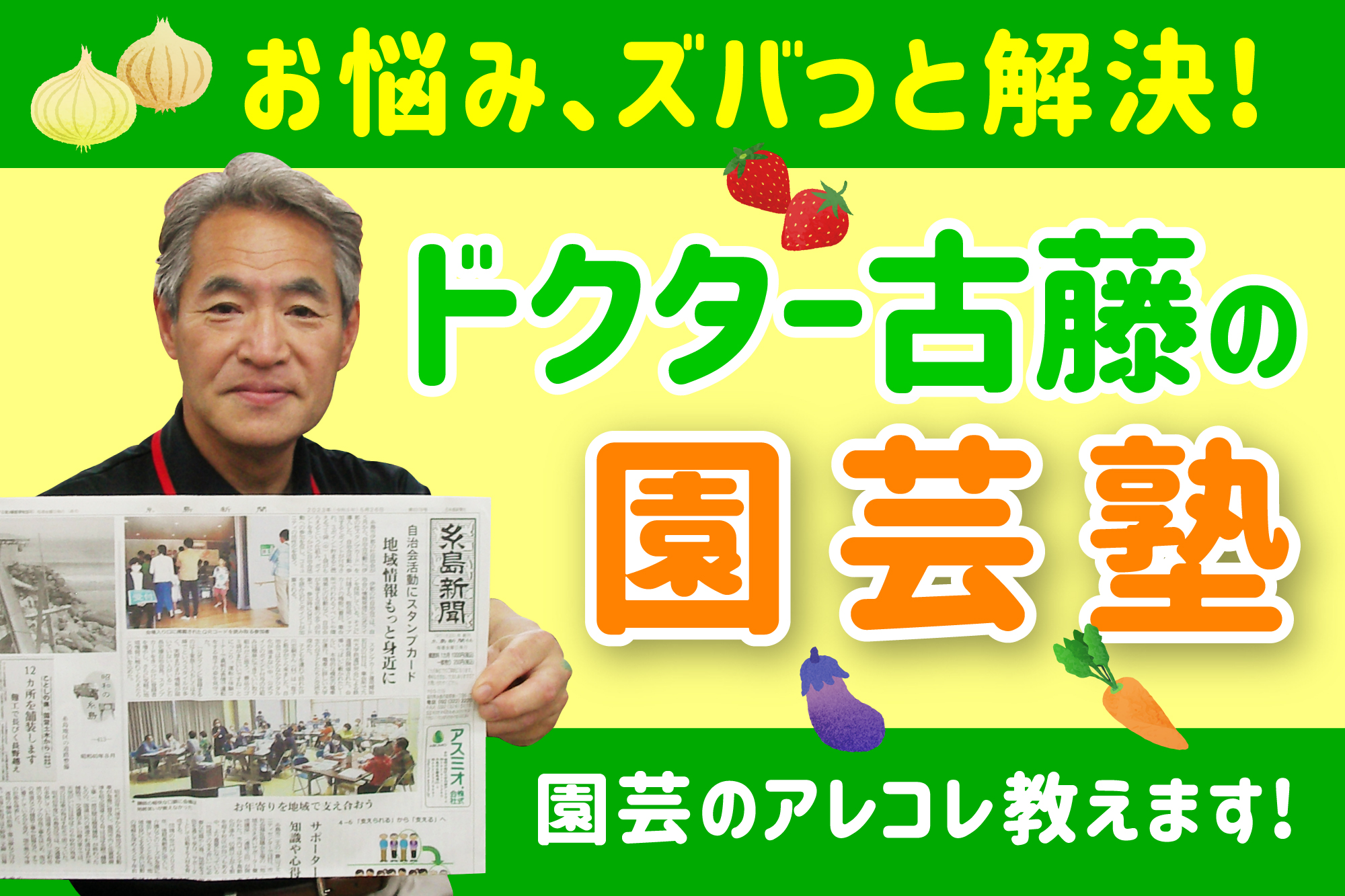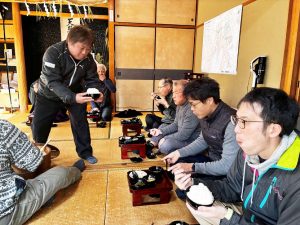柑橘類の「日焼け症」
農業暦の「処暑」(8月23日)は、時折吹いてくる心地よい夜風を感じ、次第に長くなる夜を楽しみながら秋の到来を待つ頃。なにか涼しい気持ちになれる時期の到来と思いますが、ところが、どっこい一向に涼しくなりませんね。お盆前の連休は、命の危険性を伴う記録的な大雨が発生し気温は30度を下回りましたが、その後は再び30度超えの真夏日が続きます。自然との共存である農業は、これからの台風の接近、上陸なども乗り切らなければなりません。
高温や乾燥が続く春から秋にかけ、近年、農産物で問題化しているのが「柑橘(かんきつ)類の日焼け症」。果樹類ではナシやブドウなどにも高温乾燥の影響が出ています。

農水省の報告によると、発生原因の時期は梅雨明け以降の7月下旬から9月にかけてで、品種は極早生や早生温州ミカンが中心のようです。果実表面温度が「宮川早生」で、8月では45度以上が1時間以上、9月では40度以上が3時間以上で発生するようです。
症状は①軽微=果実の陽光面が高温により、脱緑して黄緑色、黄色に変色し,症状が進むと黄色に変色した部分の果皮は硬くなる②中度=症状の程度が著しい場合、果皮はより硬くなって果形は変形し、果肉はす上がりが認められ、商品価値は低下する③重度=症状がさらに進行すると、日焼けした部分からの二次感染で炭疽(たんそ)病が発生し、落果や腐敗が発生。
生産者にとって、剪定(せんてい)や下草刈り、施肥、防除をしっかり行い、大切に育てているにも関わらず、容赦ない強い日差しは、柑橘の果皮を痛めてしまいます。
対策として、カルシウム資材を全面に散布し、果皮表面の温度上昇抑制が行われていますが、暑い時期の作業なので、生産者にとって大変な労働です。
また、堆肥など有機質の補給、敷き草、敷きワラなどにより、土壌水分の保水力を高めることも大事です。高温乾燥が続くと、柑橘類の葉からの水分蒸散率が高まり、根からの水分補給が間に合わなくなったり、土壌水分が極端に少なくなったりすると、さらに症状を悪化させてしまいます。

私の農業支援の一つが生産者の課題解決。ストレスによって弱った作物への対処や今後さらに懸念される温暖化に対する生育障害の軽減。何らかの手立てで、改善し生産者を後押しできないか、常に研究を続けています。

近年の作物生育環境は、高温乾燥が続いたり、突如として災害級の大雨が降ったり、暖冬であったりと、今までの栽培方法では、対処が難しくなってきています。農産物が高くなったという声も聞かれますが、このような自然環境の変化は、価格変動への影響も大きく、消費者の皆様も頑張っている生産者のご苦労をご理解いただくと幸いです。
(シンジェンタジャパン・アグロエコシステムテクニカルマネジャー 古藤俊二)
=糸島新聞ホームページに地域密着情報満載
※糸島新聞紙面で、最新の連載記事を掲載しています。