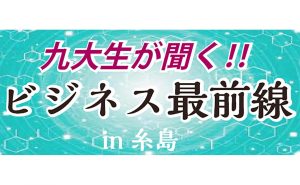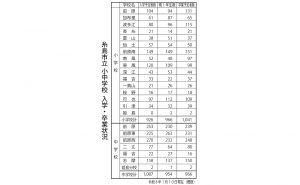ヘミングウェイ、それともサンテグジュペリにしようか。自宅の本棚に並ぶ文庫本を眺め、昔、魂を揺さぶられた文学作品を、つい読み返してみようかと思う季節になった。秋の夜長、開けた窓から流れ込んでくる心地よい風と、虫の音に心を澄まされながら、名作を通して人間の本質を問い直してみたい気分になる▼「読書の秋」。この言葉は、中国の唐時代の詩人、韓愈(かんゆ)が読んだ漢詩に由来するとされる。その詩は、こんなふうに意訳される。「秋になって長雨がやみ、涼しさが郊外の丘陵にも広がっている。夜の灯りも親しめるようになり、書物を広げるようになった」。夏目漱石の小説「三四郎」(1908年発表)で、この詩が引用されたのをきっかけに、秋の夜は読書に適しているとの考えが広がったとされる▼暑すぎず、寒すぎず、秋は体を動かすのにもいい季節。「スポーツの秋」にも、やはり由来がある。1964年10月10日に開会式があった東京オリンピック。近年の夏季五輪は7、8月に行われているが、昭和の東京五輪は、晴天になる確率が高いことから秋に入ったこの日の開幕が決まったという。そして、この日を記念して国民の祝日「体育の日」(現・スポーツの日=10月第2月曜日)が設けられた▼「芸術の秋」にも、いわれがある。1918(大正7)年に発行された雑誌「新潮」の中で「美術の秋」という記載があり、それがもとになったとされる。「大正ロマン」と呼ばれる和洋折衷の文化が花開いた時代。ノスタルジックでロマンあふれる雰囲気が秋とよく似合う▼こうした「何々の秋」というのは海外にあるのだろうか。英語では、こうした表現はしないらしい。日本の秋は、抜けるような青天を見上げることができるが、ロンドンの気候を調べてみると、秋から冬にかけては曇りや雨の日が多いという。四季がある国とはいえ、秋という季節の受け止め方が日本とは異なるのかもしれない。猛烈な暑さを乗り越え、過ごしやすさが戻りつつある今年の秋。季節の循環が感じられることに、安どしている。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)