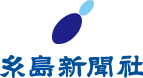かつて趣味で収集した唐津焼の酒器で、久しぶりにおいしい日本酒を味わった。粗くざっくりとした素朴な土味と、焼成中に偶発的に変化する釉薬によって生み出された景色が見どころの焼き物だ。片口に冷酒をなみなみと注ぎ、杯に移して香りを楽しみながら何度も飲み干した。「作り手八分、使い手二分」と言われ、用いることで工芸品としての美しさが完成される▼唐津焼の酒器で思い出深いのは10年ほど前、焼き物のコレクターたちが集う酒席で使わせてもらった杯。知人が持参したものだが、実は小皿だった。ゆがみや釉薬のむら、そして大きく欠けた箇所があり、別の器の破片を継ぎ合わせる呼び継ぎで繕っていた。とはいえ、漆を接着剤にし、武骨な太い線となった継ぎ目には、虹の松原に根を張った老松の大枝をイメージさせるような風格が漂っていた▼もう一つ、心を奪われたのが石はぜによって生まれた表情。器を焼成するとき、土に含まれる石粒がはじき出され、器の表面に小さな穴や亀裂をいくつもつくっていた。不完全さを否定せずに魅力を見出す「侘(わ)び寂(さ)び」の精神。それを存分に感じさせた▼唐津焼は400年以上前、唐津で焼かれるようになった。豊臣秀吉の朝鮮出兵のとき、連行された陶工たちによって生産は肥前の各地で本格化。「一楽二萩三唐津」と言われ、茶陶として茶人に好まれてきた。ただ、知人は茶の湯で使う茶碗(ちゃわん)など格式の高いものではなく、普段使いの小皿を愛で、それを杯に見立てて愛用している▼しばらく使っていなかった唐津焼の酒器で晩酌を演出してみたのは、九州国立博物館で開催中の特別展「平戸モノ語り 松浦(まつら)静山と熈(ひろむ)の情熱」の観覧がきっかけ。江戸時代後期に、現存する国内最大級の大名家コレクションを築いた平戸藩主父子の物語。先祖や地域ゆかりのモノを収集、修理して後世に残すことに情熱を注ぎ、未来の人々に対して藩主としての責任を果たした。知人が呼び継ぎの小皿を大事にしているのも通じるところがある。モノは思いがあってこそ、伝世する。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)