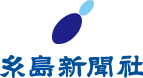野北村・お松の悲運 ②
鶴太郎は、まだ初々しい丸髷(まるまげ=新妻の髪型)姿の女性と何やら楽しそうに話している。女性は間違いなく若妻である。「あの鶴さまが、いつの間に奥さまを…」とつぶやくと、お松の足はガタガタ震え、顔は真っ青になり、お松の初恋はもろくも崩れ去った。
お松は、お栄の手を振り切り無我夢中で千歳屋に駆け戻ると、店の人には何も言わずに自分の部屋に飛び込んで泣き伏した。
やや遅れて店に戻ったお栄は、鶴太郎から「銀の簪のことや茶遊びのことを家人に知られ、叔父の娘と無理やり結婚させられた。済まぬがこの鶴太郎のことは死んだと思って諦めてくれ」というお松への伝言を頼まれたことを話した。
ほのかな初恋には破れたが、気を取り直して「結婚の約束を交わしていたわけでもない」と自分に言い聞かせ、再びまめまめしく働きだした。
年も変わってお松も十九歳の春を迎えた。お松はますます美しくなり、女将や姉さん芸者、女中からも可愛がられ、客の評判も良かった。そんなお松に、最近足しげく通ってくる一人の青年僧がいた。
この青年僧は野北村に近い村の素厳寺という寺の住職をしていて、名を実念と言った(寺名も僧の名も仮りの名)。素厳寺といえば、志摩や怡土では名の知れた裕福な寺で、美青年の実念には、どんな美しい坊守(ぼうもり=奥さん)が来られるかと、村娘の間では噂になっていた。
その実念がある日、檀徒の総代たちと寺の用事で博多に出た折、夕食をとるつもりで千歳屋に立ち寄り、お松と知り合ったのである。同じ志摩の者という親近感が若い二人を急速に接近させた。それに実念は僧という立場から、お松を今の境遇から救い出してやりたいという気持ちもあった。
以来、実念は何かと寺の用事を作っては博多に行き、千歳屋の暖簾をくぐってお松との逢瀬を楽しむようになった。
「お松さん、坊主の身で茶屋遊びをするなどと心の中で笑っておられるであろうが、私は茶屋遊びの気持ちではない。あなたをひと目見てからは朝夕の勤行(ごんぎょう)も力がこもらず、あなたの顔が浮かんでくる。これも私の精進と学問が浅いためで、こうなったらあなたなしでは生きられぬ。お松さん、どうか実念のお願いだ、私の嫁になっておくれ」と、真剣な目でお松に頼んだ。
お松は、幼いころ母に連れられて行ったことのある素厳寺、その寺の若い住職から、こともあろうに貧しい漁師の娘、まして芸者の私を妻に所望されるとは、まるで夢のようだと驚いた。
「まあ実念さま、御冗談を…、私のような者がどうして…」
「決して冗談などではない。私の妻はあなたと決めた。檀徒の方々から異論も出ようが、私の気持ちは変わらぬ。きっと迎えに来るから、その日まで待っていてほしい。千歳屋のご主人にも私から話しておくから…」