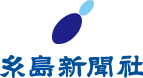野北村・お松の悲運 ③
田舎娘をここまで真心込めて接してくれ、妻にしたいとまで言ってくれたのは、お松にとって実念が初めてであり、お松の目からはハラハラと涙がこぼれた。
素厳寺の若住職の実念が、茶屋芸者を身請けし妻にするという話は、瞬く間に志摩と怡土の村々に広がっていった。もちろん檀徒からは猛反対の声が上がったが、思いつめた実念の一心は変わることなく、周囲の声を説き伏せ、いよいよその日を迎えた。
日ごろから心がけの優しいお松だけに、千歳屋の主人夫婦や芸者、女中をはじめ店の者全員がお松に引き出物を渡し、祝い唄でお松を送り出してくれた。
夢にまで見た懐かしい筑紫富士の姿を仰ぎながら、お松はいったん野北村の実家に落ち着いた後、素厳寺の門をくぐった。檀徒の反対を押し切っての結婚だけに、式は簡素であったが、お松にとっては夢のような感激だった。
式は滞りなく済み、翌日からお松は坊守としての生活が始まった。お松は賢い女で「寺は檀徒の皆さまで支えられている。私は夫の実念に尽くすと同様に、檀徒の皆さまにも尽くさねばならぬ。決して後ろ指を指されるようなことをしてはならない」と覚悟した。
お松のいじらしく、甲斐甲斐しい勤めぶりに、最初は反対していた檀徒たちも次第に「いい坊守さんが来てくださった」と、喜ぶようになっていった。このままなら、お松の一生は幸福に満ちたものになるはずだったが、不幸は突然やってきた。
素厳寺の坊守となって半年ほどが過ぎたある日、お松が庫裏で針仕事していたところ、厨(くりや=台所)から夕飯の支度している女中の大きな声が聞こえてきた。
「お松に合わせろ!」
男の大声にお松の顔は見る見る青くなった。お松には権太という一人の兄がいたが、物心がつくころから暴れん坊となって家を飛び出し、博多で博打打ちの仲間に入っていた。けんかで片方の目がつぶれていたため、仲間からは「片目の権太」と呼ばれていた。お松が千歳屋で働いているときも二、三度店にやってきて女将から小銭をせしめたりしていた。
「兄さんがどうしてここにまで…。私の幸せまで踏みにじるつもりだろうか」
お松が厨に行くと、着物の尻裾をまくり、女中相手に「お松を出せ」と怒鳴っている権太がいた。お松は目に涙をため「兄さん、あなたはこんなところにまで来て、私を苦しめようというのですか」と言うと、
「お前が出世して坊主の嫁になったと聞いたからお祝いを言いに来たのに、茶の一杯も出さない上に、苦しめるとは何という言い草だ」
「それなら、もっと大人しくしてはどうです。間もなく和尚さまもお帰りになりますから」