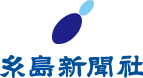書斎を整理していると、金髪の少年が小さな星の上に立っている表紙絵の本が目に留まった。フランスの作家サン・テグジュペリの「星の王子さま」。家族がしまい込んでいた本を手に取り献辞を読んでみると、子どもだったころのおとなに、ささげる作品だという▼「おとなは、だれも、はじめは子どもだった。しかし、そのことを忘れずにいるおとなは、いくらもいない」(内藤濯訳)。半世紀前、少年だったころの自分と出会えるのではないかと思い、読み進めた。易しい言葉で書かれているが、物語全体が暗喩に満ち、いろんな読み方ができ、実は難解だ▼何度も読み返すうち、この物語で貫かれているのは、愛情の絆を共に築き上げた相手が最も大切な存在であるということだった。地球に旅してきた王子さまにとって、その相手は、ふるさとの星に残してきた一輪のバラ▼ふるさとにいたとき、バラは自身の美しさを鼻にかけ、思いつくままに自分を引き立たせる話をし、ずるそうに振る舞った。王子さまは、バラとの難しい関係から逃げ出そうと、ふるさとを後にした。だが、旅に出て、王子さまはバラのおかげで、ふるさとの星がいい香りと明るい光に包まれていたことに気づく▼王子さまは幼さゆえ、バラの目に見える振る舞いにとらわれてばかりいて、バラとの間に愛情の絆が築かれているということが、分からなかった。「心で見なくちゃ」「かんじんなことは、目に見えないんだよ」。物語で何度も出てくる言葉。おとなになると、収入であったり、自身の能力であったり、目の前にある現実に振り回され、本当に大切なものを見失ってしまう。日頃の生活で築いた愛情の絆。子ども時代に戻って周りを見つめ直してみませんか。
目次