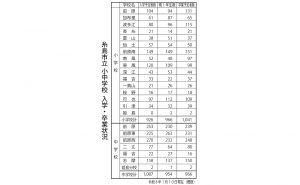人と会話しているかのような感覚で文章を生成する対話型人工知能「チャットGPT」の進化などにより、仕事や暮らしにさまざまに関わるようになってきた人工知能(AI)。生産性向上などが期待できる一方、あまりにも速い開発ぶりに、どんな影響が出てくるのか見通せず、不安も感じる▼AI自体は、豊かな経験に培われた人のような価値観をもたないという。このため、差別や偏見を助長したり、偽情報による社会の混乱を引き起こしたりしないよう、利用する人の側に倫理観が求められる。善悪を判断して道理をわきまえる人の心のはたらき、智慧(ちえ)を身につけることがAI時代にはとても大切だと思う▼智慧について、昔読んだ本を紐解き、仏教の視点から学び直してみた。「NHK文化セミナー 対話の仏教経典・ミリンダ王の問い」(著者・石上善應)。紀元前2世紀、西北インドを支配したギリシャ人のミリンダ王と仏教僧との間で行われた仏教教理についての問答を解説している▼こんな対話が盛り込まれている。「尊師よ、知識と智慧とは同一のものでしょうか」。王の問いに、仏教僧は「同一のものです」と答えた。著者はこの問答を分かりやすく説くため、お釈迦さまのたとえ話を記す。お釈迦さまは弟子たちにこんな質問をした。舟も橋もない川を渡るため、いかだをつくって渡った男が向こう岸に着いた。いかだは便利で役に立つだろうと思い、男はそのままかついで陸地を進んでいった。いかだは役に立つのだろうか▼弟子たちは、みな「役に立ちません」と答えた。男は、いかだが自分のために役に立つという「知識」を捨てきれなかった。では、そこにいかだを置いていったら、どうなっただろう。ほかの人が便利に使えることができた。自分だけでなく、人のことまで思いを巡らせた行動に導く。それは「智慧」によるものだと、この本は教える。「知識と智慧は同一」というのであれば、本物の知識とは、畢竟(ひっきょう)、智慧と変わらないということか。そして、AIと人の智慧との関係性。それを正しく築いていくのはこれからだ。
(糸島新聞ホームページに地域密着情報満載)