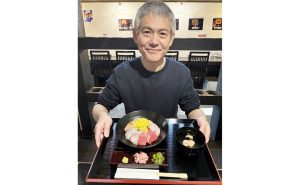ーーー印象深い10の生き物紹介ーーー
野鳥の鳴き声の録音をはじめ、自然の動植物を観察することが大好きな田中良介です。私が普段、自然観察をする場所は福岡市と糸島市の里山ですが、今回は糸島市の北部と南部の野山を散策して出合った昆虫や野草、野鳥、その他の生き物のうち、印象深かった10の生き物たちを写真とともに紹介します。
(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)
シオカラトンボ

トンボやチョウ、バッタの仲間はとくに大好きです。シオカラトンボはもっともポピュラーなトンボです。名前の由来は塩を振りかけたように見えるその体色からきています。オスは成長の過程で、ムギワラ色になることもあります。
カラスアゲハ

大型の美しいアゲハチョウで、体色が黒いのが名前の由来です。幼虫は緑色をしていて好んでカラスザンショウ、コクサギ、またミカン科の植物の葉を食べます。夏季は春の個体より大きくなります。
トノサマバッタ

その名の通り、バッタの王様と言っても過言ではないほど堂々とした姿をしています。緑色系と褐色系があり、大きさはオスが3.5~4センチ、メスがやや大きくて4.5~6.5センチです。クルマバッタの別名で呼ばれることもあります。
ノシメトンボ

ノシメとは熨斗目のことで、このトンボの胴体の模様が熨斗目に似ているところからこの名がついたとされています。4枚の羽根の先端に黒い色があります。やや数が少なく出合うことは難しい種です。
ベニシジミ

春から夏によく目にする小さなかわいいチョウで大きさは1.5センチほどです。アザミやヒメジョオンなどの野草にとまっているのをよく見ます。幼虫はスイバやギシギシなどの葉を食べて成長します。
クロツラヘラサギ

越冬のために朝鮮半島から秋~冬に渡って来ます。黒いクチバシがヘラのように横に平たいのでこの名がつきました。サギの仲間ではなくペリカン目トキ科の鳥です。春に北に帰り、朝鮮半島西側などで繁殖します。この写真は、糸島市の弁天橋近くの岩場で撮影しました。
カナヘビとナツズイセン

ナツズイセンはヒガンバナ科の野草。美しい花を撮影していたら、トカゲの仲間カナヘビがひょっこりと顔を出してくれました。カナヘビは体長が18~25センチですが、尾が長くて全体の三分の二を占めます。コオロギ、小さなバッタ、芋虫、ミミズなどを餌にして暮らしています。
小鳥を食べたアオダイショウ

アオダイショウは2メートルにもなるわが国最大のヘビ。毒はなく臆病なので近づくとすぐに隠れる。しかし、この個体は私の知人が庭の木にかけた巣箱で繁殖したシジュウカラのヒナを襲って全部を食べてしまった。偶然通りかかって撮影した1枚。残酷だが、これも自然の営みの1シーンに過ぎない。
カササギ

九州ではカチガラスとも呼ばれているカラスの仲間です。豊臣秀吉の朝鮮出兵の折、佐賀と柳川の大名が持ち帰り、自然に放したとされています。なぜか九州北部に集中して生息する地域限定版の野鳥です。
アザミの花とハナグモ

ハナグモは明るい緑色をしていて、体調は1センチ弱。アザミなど花の裏に隠れていて、小さなハナアブなどが吸蜜に来ると、さっと現れて虫を捕らえます。きれいな花には毒があるのではなくて、危険があると言う見本のような自然の営みです。