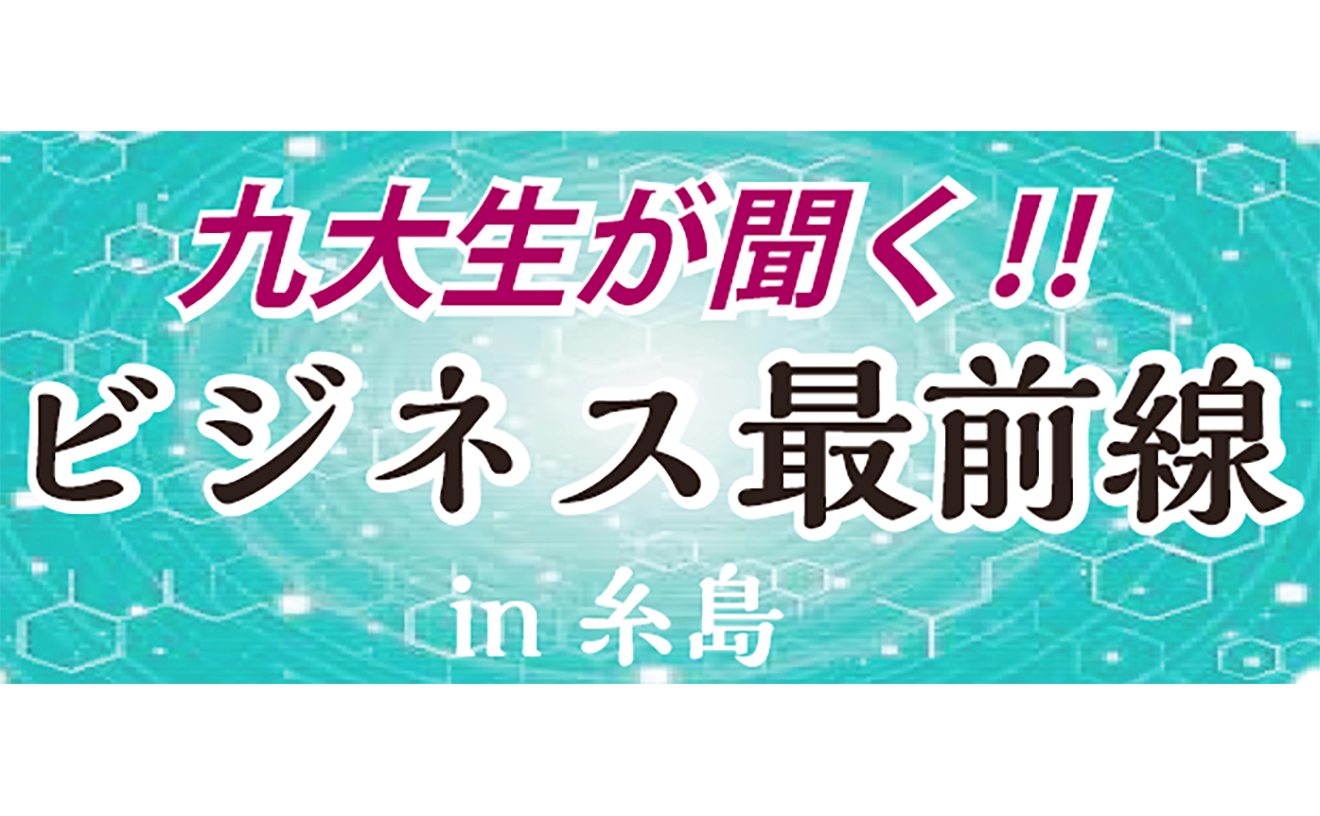北伊醤油㊤ 社長 山上弘司さん(43)
このコーナーは、九州大学のインターン生が糸島エリアで活動している団体や企業を取り上げ、魅力を紹介しています。今回は、共創学部3年の加藤千穂が北伊醤油(しょうゆ)社長の山上弘司さん(43)に、天然醸造の伝統的な製法を守り、本物の味と香りを究めた醤油造りについてうかがいました。

-主に天然醸造で醤油を造られていますが、どのような醸造方法なのでしょうか。
「天然醸造は、全国の醤油生産量のうち1%にも満たない醸造方法です。当社では、蔵のすぐ後ろにそびえる船越山の天然水、大豆(糸島産)、小麦、塩を使い、初代から約130年間変わらない方法で醤油を造っています。麹菌(こうじきん)を使い、大豆のタンパク質や小麦のでんぷん質を分解、発酵させたもろみと呼ばれるもの、を木桶(きおけ)の中で、2年半以上寝かせています」
-伝統的な天然醸造にはどのような味の違いがあるのですか。
「100年以上受け継がれてきている木桶には酵母菌の一種である、さまざまな後熟酵母がすみついています。子供が恩師に出会うと立派に育つように、良い酵母菌がいると、それによって大豆や小麦が発酵を促され奥行きのある芳醇(ほうじゅん)で香りのいい醤油になっていきます。原材料の持っている栄養素がなくなると、発酵は止まってしまいますが、3年間は発酵し続けるため、その間は寝かせ、一番おいしくなった状態のものをお客様に提供しています」
-年々温暖化が進んでいますが、温度管理は難しくなっていますか。
「実は、温度管理で大変なのは夏よりも冬なんです。味に深みを出すためには、四季の中で温度を変化させ菌の働きにも変化をつけさせないといけません。そのためにはきちんと冷ます工程も必要です。7年ほど前までは、自然の気温の中で発酵させていましたが、近年の暖冬では蔵の温度を1桁台まで冷ますためにエアコンを使用しており、コストがかかってしまっています。一方、夏は発酵を促すために蔵を高温に保つので、従業員が木桶のもろみをかき混ぜる作業が大変になっています」

次回は、お客様に向き合う姿勢についてお話をうかがいます。
(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)