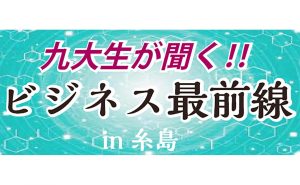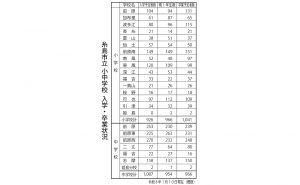26日、伊都国フォーラム 専門家が多角的に
伊都国の王墓として知られる平原遺跡の発掘から60年を記念し、第9回伊都国フォーラム「倭国形成と平原王墓」が26日午前10時から、伊都文化会館大ホールで開かれる。国宝の内行花文鏡をはじめ、最新研究で明らかになった中央アジア由来のガラス製連玉など、平原遺跡が持つ国際性と倭国形成における役割について専門家が多角的に意見交換する。参加無料、申し込み不要(定員600人)=写真はチラシ。

平原遺跡(糸島市有田)は1965(昭和40)年1月18日、農作業中に井手信英さんらが鏡の破片を発見。同年2月4日から5月17日まで、地元考古学者の原田大六氏を中心に約100日間の発掘調査が行われた。直径46.5センチの国内最大級の銅鏡「内行花文鏡」など多数の副葬品が出土。06年に一括で「福岡県平原方形周溝墓出土品」として国宝に指定され、来年で指定20周年を迎える。
今回のフォーラムでは、弥生時代から古墳時代への転換点に位置する平原遺跡の重要性に焦点を当てる。月形祐二市長は「約2000年の歴史の積み重ねは他の自治体が簡単に真似できない価値。ブランド糸島を構成する大切な要素」と強調。市文化課は「平原遺跡は国内で最も有名な遺跡の一つだが、まだ多くの謎を秘めている。その謎こそが遺跡の魅力」と語る。
当日は、市文化課の平尾和久さんが「平原王墓の調査と伊都国の性格」と題して、発見から現在までの歩みを報告。続く基調講演では、柳田康雄さん(國學院大學博物館客員教授)が「平原巫女王墓(みこおうぼ)とイト国が果たした役割」について講演。柳田氏は学生時代に1965年の発掘調査に参加した経験を持ち、平原王墓を「巫女の王が葬られた墓」とする独自の説を展開する。
田村朋美さん(奈良文化財研究所主任研究員)は「ユーラシア的視点からみた平原王墓出土玉類の国際性」と題し講演。最新研究により、ガラス製連玉がカザフスタンなど中央アジアを経由して糸島に持ち込まれたことが判明。鏡だけでなく玉類も高い国際性を示していることを解説する。
南健太郎さん(京都橘大学准教授)は「大型化する弥生墳墓と平原王墓」について講演。平原遺跡の墳丘は9.5メートル×13メートルと小規模ながら、副葬品は極めて豪華。日本最大級の弥生墳墓(約83メートル)がある岡山での研究経験を持つ南氏が、墳丘の大きさと副葬品の豪華さの関係から平原王墓の特異性を分析する。
後半のシンポジウム「伊都国最後の王墓、平原王墓に迫る」では、内行花文鏡が国産か中国からの輸入品かという論点も議論される。柳田氏は「40枚の鏡の大半は糸島・福岡で製作」と主張する一方、南氏は「全て舶載品」との立場を取る。コーディネーターは河合修さん(市文化課)が務め、倭国形成期における糸島の有力者の役割を探る。
平尾さんは「弥生時代から古墳時代への転換点に位置する平原遺跡。鏡を重視する思想が古墳時代に継承されており、倭国形成に糸島の王が重要な役割を果たした可能性がある」と意義を説明する。
(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)