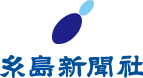野北村・お松の悲運 ①
今から百六十年程前、江戸時代が終わろうとしていたころの話である。
博多の石堂川のほとりに「千歳屋」という料亭があった。この料亭には、お松という博多界隈では知らない人がいないほどの美人芸者がいた。
お松は野北村の漁師の娘だったが、暮らしが貧しかったため、芸者となったのであった。歳は十八ながら、家庭のことを思い一生懸命に働いていた。
そんなお松の心を最初に捉えたのは、掛町筋の老舗の若旦那の鶴太郎であった。鶴太郎はお松より四つ年上の二十二歳で、若さと遊里の客には珍しい誠実な若者だったので、お松の方も次第に鶴太郎に心を寄せるようになった。
ある日の早朝、お松が鏡台に向かって化粧をしながら、引き出しの中から一本の銀の簪(かんざし)を取り出し、そっと唇にあてた。その簪は鶴太郎がくれたもので、蔦(つた)の模様が平打ちされていた。
「私も幸福がつかめるかも知れぬ。鶴太郎さんと添われるかも…」。そんなことを思い浮かべながら、窓の外を流れる石堂川の水面を眺めていた。初秋の博多の街を川面に映して、ゆっくりと博多湾に流れていく。その、ずっと向こうには野北の里がある。
「家のことは心配するな。苦しいだろうが、暫くの辛抱じゃ。身体を大切に、一日も早く年季を済まして戻っておいで」。貧乏だったが、優しい母の面影が浮かぶ。「お母さーん」と、お松は大声で川に向かって呼んだ。
「何も知らない博多の街に来た時は怖かったけど、店では女将さんも姉さんたちも優しく、可愛がられています。そして、いまは鶴太郎さんという方が…」。母に報告するかのようにつぶやいていたお松は、ハッとして顔を赤らめ、簪(かんざし)を引き出しに戻した。
お松は知らなかったが、鶴太郎がくれた簪は、鶴太郎の家の家宝であった。鶴太郎の母が嫁いでくるときに、京都でわざわざ誂(あつら)えたものであった。慶応元年(1865)五月、福岡藩が出した諸事節約の布令によって金や銀の髪道具も使えなくなり、以来、店の奥に保管されていたものであった。
「お松さん、箱崎の放生会に行かない?鶴太郎さんに会えるかもしれないよ」。トントンと階段を上ってきて声を掛けたのは、同じ野北村から奉公に来ている女中のお栄であった。二人は幼馴染で女同士、寂しいときはいつも慰めあうという、大の仲良しである。
「そうね、行ってみようかな」。お栄に誘われてお松もその気になった。お松は最近鶴太郎に会っていなかった。あれほど足しげく通っていたのに、「病気でもしているのではないか」と気になっていたところだったので、お栄の誘いがうれしく、すぐに身支度を整えた。
放生会の人波をぬって神前でお参りし、お汐井道を浜の方に歩いていると、お栄がポンとお松の肩をたたいた。「お松さん、私が思った通りだよ。ほら、あそこに鶴太郎さんが…」と、指さす方に目をやれば、路傍の掛茶屋の床に恋しい鶴太郎さんが腰かけている。お松は思わず声を掛けようとしてハッと息をのんだ。