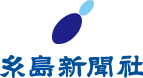自宅庭の畑で育てている自然薯が支柱に張った網にツルを伸ばし、たくさんのムカゴを付けている。収穫するにはまだ早いが、秋には小指の先ほどの大きさに膨らみ、塩ゆでにすると、ビールのつまみになるから、何とも楽しみだ▼自然薯を栽培しようと思ったのは、隣の唐津が名産地だと、地元の農家から聞いたのがきっかけ。その話が何ともユニークだった。夏目漱石の小説「吾輩は猫である」(1905年発表)を読んでいたら、唐津の自然薯の話が書かれていたのだという▼確かめてみると、吾輩の主人(飼い主)の家に泥棒が忍び込み、奥さんの枕元に大事そうに置いてあった釘付けの箱を盗んでいった。中身は、親しい間柄の唐津出身の男性からお土産にもらった山の芋(自然薯)だった。調べに来た巡査の指示で、盗難の告訴状を書く夫婦にはこんなやりとりが…。「山の芋のねだんまでは知りません」「そんなら十二円五十銭位にして置こう」▼明治時代の1円は現代の2万円相当の価値があるとされ、吾輩の主人は、唐津の自然薯に今の感覚で25万円の値段をつけた。法外な値段にあきれたように妻が反論し、落語のような軽妙なやりとりが続いていく▼ともかく、明治時代後半、唐津で掘り出された自然薯は、はるばると東京へと送り届けられるほどの高級品だったようだ。そのブランド力をよみがえらせようと、唐津では、若手農家が農薬・化学肥料を使わない栽培に取り組んでいる。温故知新-。過去からいろんなヒントを得て、わくわくしながら今に生かしてみませんか。
《糸島新聞連載コラム まち角》