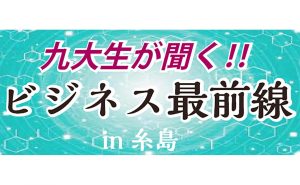矢野寛治さん 福岡市総合図書館で講演
糸島郡今宿村(現福岡市西区今宿)出身の女性解放運動家で、関東大震災の混乱のさなか、憲兵に虐殺された伊藤野枝(1895-1923)と、その子どもたちの生きざまを深く見つめる講演会が福岡市早良区の福岡市総合図書館であった。評伝「伊藤野枝と代(だい)準介」の著者、矢野寛治さんが講師を務め、「真実一路に生きた伊藤野枝と、その子どもたち。」と題し、正しいと思えば、即行動に移した野枝と、その生き方を受け継ぐような歩みをした子どもの生涯について語った。

矢野さんの評伝に登場する代準介は野枝の叔父で、深い愛情をもって物心両面で野枝を支えた。矢野さんの妻、千佳子さんが代のひ孫に当たり、矢野さんは妻の実家に残されていた代の手書きの自叙伝をもとに、野枝や野枝に関わった人々の人物像を調べて評伝を著した。9月21日にあった講演会では、自叙伝から明らかになった野枝の人生も交えて語った。
野枝は、元英語教師で翻訳家の辻潤、無政府主義者の大杉栄の2人の夫との間に7人の子どもを授かった。矢野さんは「一番、母親に似ている」として、四女のルイ(1922-96)の生きざまについて触れた。ルイは生後1歳3カ月で、野枝と大杉を失い、今宿にある野枝の実家で育てられた。矢野さんは、博多人形の彩色職人となったルイが手掛けた人形を披露した後、韓国人被爆者支援、反戦などの市民運動に関わった活動家としてのルイについて述べ、記録作家、松下竜一による「ルイズ-父に貰(もら)いし名は」の刊行後、自らも自分史「海の歌う日」などの執筆活動をしたことを紹介した。
矢野さんは、野枝の真実一路について「どんな確執や桎梏(しっこく)があろうとも、自分の心に忠実に生きた。多くの人を傷つけたりもしたことでしょう。ただ、おもねるやへつらうことを一切しない生き方だった」との見方をした。
講演会は、同図書館で26日まで開催中の常設展示「海の歌う日-伊藤野枝の子どもたち」を記念して行われた。同展では、糸島新聞が64年から翌年にかけ、代の生きざまを連載した「或(あ)る男の一生 元岡村生まれの快男児、代準介」の記事も展示されている。
(糸島新聞社ホームページに地域情報満載)