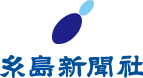猛暑に蝉(せみ)時雨が加わり、にぎやかな夏が到来した。江戸前期の俳人、松尾芭蕉は、皆さんもご存じの通り「閑(しずけ)さや岩にしみ入る蝉の声」と詠んだ。実は、この句のセミの種類を巡り、昭和の初め、文人の間で論争が起きた▼発端は歌人の斎藤茂吉が雑誌で、この句のセミはアブラゼミと断じて発表したことだ。これに対し、夏目漱石門下の独文学者小宮豊隆がニイニイゼミだと主張した。芭蕉がこの句を詠んだのは山形の山寺。訪ねた日は新暦に直すと7月13日で、実地調査の結果、この時期にアブラゼミはまだ鳴かず、鳴いているのはニイニイゼミと判明。茂吉は自説をあらためた▼ただ、この逸話で注目されるのは、茂吉がこの句からアブラゼミの強い鳴き声を感じ取っていたことだ。「群蝉(ぐんせん)の鳴くなかの静寂」と、とらえていた。一方、小宮は「岩にしみ入る」という句にふさわしいのは、細く澄んで「糸筋のように」鳴くニイニイゼミの声だと論じた▼小学生時代、学校でこの句を学んだ時、イメージしたのは茂吉と同じ「群蝉」のような強烈な鳴き声。勢いよく鳴くからこそ、「閑さ」がより際立つのだと、今も思っている▼芭蕉は俳諧の理念として「不易流行(ふえきりゅうこう)」を掲げた。いつまでも変わらないことを表す「不易」と、時代に応じて変化することを示す「流行」。相反する概念を一つにし、不変の中に変化を取り入れるというものだ。山寺の静寂さが不易であれば、夏だけの命を謳歌するセミの声は流行であろう。不易と流行の調和。それを感じた瞬間、心は深遠な世界へと導かれる。
《糸島新聞連載コラム まち角》